朝ドラ『あんぱん』で八木信之介(妻夫木聡)が引用したシェークスピアの名言「逆境が人に及ぼすものこそ輝かしい」は、単純に言えば、困難や苦しい状況が、人間に大きな価値や光をもたらすという意味です。
この言葉が引用されたシェークスピアの戯曲『お気に召すまま』では、不当に追放され、森で質素な生活を送る公爵がこのセリフを言います。公爵は、王宮での華やかで偽りの多い生活よりも、森での厳しくも真実の生活の方がずっと良いものだと考えていました。
この名言が持つ教訓は、主に以下の2つに集約されます。
- 逆境は真の価値を教える: 困難な状況に置かれることで、それまで当たり前だと思っていたものの価値や、本当に大切なものが何かを深く理解できます。
- 逆境は人間を成長させる: 苦しい経験は、人を強くし、知恵を与え、新しい能力を開花させます。逆境を乗り越えることで得られる力は、成功や順風満帆な人生では決して得られないものです。
『あんぱん』では、この言葉が学歴がないことを気にする蘭子を励ますために使われました。つまり、学歴という「順風満帆」な道がなくても、自分の置かれた状況を嘆くのではなく、そこで得られる経験や学びこそが、彼女を輝かせる真の価値なのだと伝えようとしているのです。
「逆境が人に及ぼすものこそ輝かしい」というシェークスピアの言葉は、困難を乗り越えた先には必ず良いことがある、という希望を私たちに与えてくれます。
生活困窮者が希望を持つことができるのでしょうか
今日を生きるのが精一杯の「その日暮らし」をしている人々にとっては、この言葉の輝きは見えないかもしれません。それは以前、困窮者自立支援員として活動していた時に実感したことです。
貧困は自己責任だけではありません。社会全体の問題です。一人ひとりが声を上げ、行動することで、貧困のない、より良い社会を築き、誰もが輝ける未来を創造できるはずです。しかし・・・
「社会全体で手を差し伸べること」では、もはや間に合わない
貧困は「社会全体で手を差し伸べる」という言葉だけでは解決できない厳しい現実があります。希望を持つことが難しい状況にある人々にとって、抽象的な言葉は届きません。具体的な行動と、その積み重ねによってしか、希望は見出せないのかもしれません。
貧困の解決には、個人の努力やボランティア活動だけでは限界があります。根本的な解決のためには、**「制度の変革」と「社会意識の変革」**という二つのアプローチが必要です。
制度の変革:貧困の連鎖を断ち切るための具体的な制度改革
現状の支援制度は、必要な人に必要な支援が届きにくい、という課題を抱えています。これらを改善するためには、以下のような具体的な制度改革が求められます。
- 所得の再分配機能の強化: 所得の低い人々への支援を厚くするために、税制や社会保障制度を見直し、富裕層や大企業からより多くの税金を徴収し、それを貧困対策に回す仕組みを強化します。
- 教育格差の是正: 子どもの貧困を解決するためには、教育格差をなくすことが最も重要です。質の高い教育を誰もが無償で受けられるように、給付型奨学金の拡充や、貧困家庭の子どもを対象とした学習支援の制度化を進めます。
- 住宅支援の拡充: 安定した住居は、生活の基盤です。住宅確保給付金制度の対象者を広げたり、公営住宅を増やしたりすることで、住居を失う不安を解消し、再出発を支援します。
- 雇用の安定化と賃金の底上げ: 非正規雇用を減らし、正規雇用を増やすための政策や、最低賃金の引き上げを継続的に行うことで、働くことで貧困から抜け出せる社会を目指します。
これらの制度改革は、緊急かつ短期的な生活困窮者救済手段です。しかし相談支援をしていて思ったことは、本当に困っている人は相談に行ってみようとする気力さえなくしているという事実です。
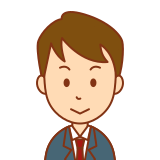
私が所属していた生活困窮者支援センターでは、対人支援が未経験で福祉関係の資格もない支援員ばかっりでした。当然、支援内容は形式的で一時的救済手段でしかありませんでした。多くの場合、国が事業として実施する施策は形式的になってしまいがちです。そして多額の事業予算が組まれていたとしてもそれはどこかに消えていて、直接貧困者にはわたっていません。現場で直接活動する人たちは非常勤採用の低賃金ですから当然優秀な人材が集まるわけはありません。それについての実態を詳しく知りたい方はどうぞコメントをください。
社会意識の変革:貧困は「自己責任」ではないという認識を広げる
貧困は「努力が足りない」「自己責任」だという考えは根強く、これが支援をためらわせる原因になっています。この認識を変えることが、社会全体で支え合うための第一歩です。
- 貧困の「見える化」と啓発: メディアやSNSを通じて、貧困の実態をより多くの人に伝える活動を強化します。見えない貧困を「見える化」することで、他人事ではなく、自分たちの社会の問題だと認識してもらうことが重要です。
- 当事者の声を社会に届ける: 貧困を経験した当事者が自らの声を語る場を設けることで、統計データだけではわからない、個別の困難や苦しみを社会に伝えます。これにより、共感が生まれ、支援の輪が広がります。
- 連帯感の醸成: 「困った時はお互い様」という地域の連帯感を再生させることも重要です。子ども食堂や居場所づくり活動などを通じて、地域コミュニティの中で自然に助け合える関係性を築きます。
希望はどこにあるのでしょうか
シェークスピアの言葉は、逆境そのものが希望を生むと語ります。しかし、今の日本では、逆境に置かれた人々が一人でその輝きを見つけるのは困難です。
希望は、「困難の先にある輝かしいもの」を、個人が一人で探すのではなく、社会全体で光を当て、共に歩むことで見出されるものです。
貧困の解決は、私たち一人ひとりの小さな行動から始まります。それは、寄付やボランティアだけでなく、社会問題に関心を持つこと、そして「貧困は社会の問題」だと声を上げることです。
このような行動の積み重ねが、やがて制度や社会全体の意識を変える大きなうねりとなり、真の希望を生み出すのではないでしょうか。
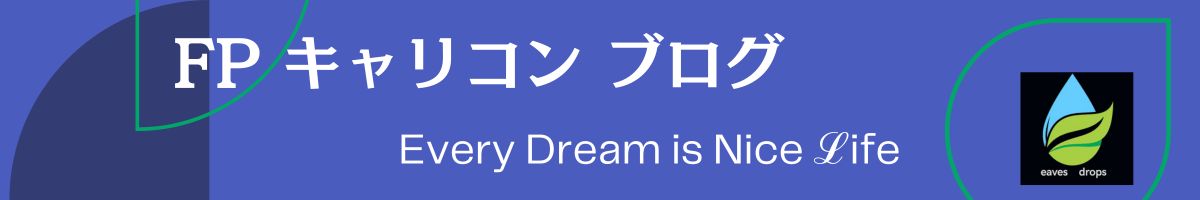
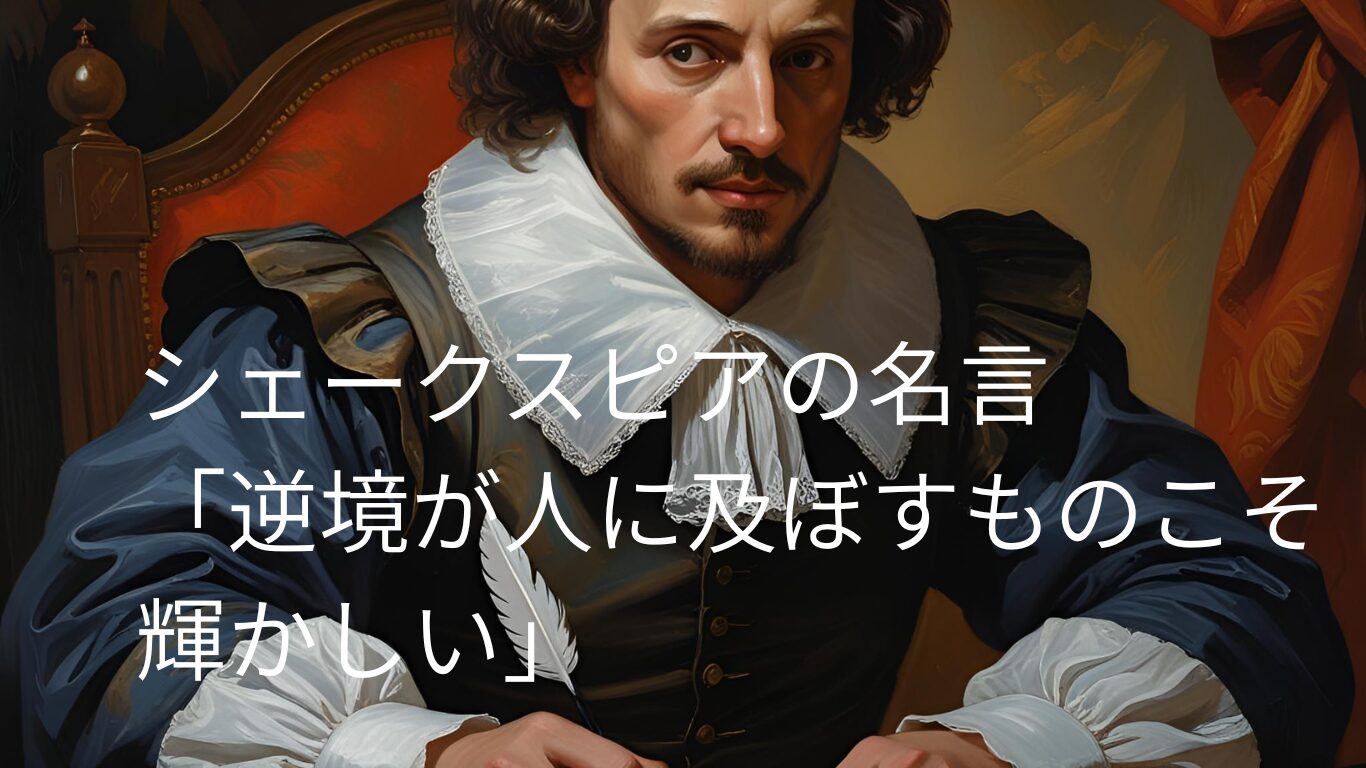
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/360a1a82.01d332bf.360a1a83.af039a24/?me_id=1355729&item_id=10000303&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ff032051-hanamaki%2Fcabinet%2F09531388%2Fr7-6%2Fat-bluanp1_assyuku.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b5e901b.0c12d4f6.4b5e901c.f82c4b87/?me_id=1342148&item_id=10000970&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ff192023-fujiyoshida%2Fcabinet%2F06960653%2F09063425%2Ff112-005-t372-s-r.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
コメント