73歳でお米農家を辞めた理由
耕作面積2ヘクタール(坪数で約3000坪))の米作農業を辞めた農家さんに聞いた話を紹介します。会社勤めをしていたのですが、親が高齢のため農業(田んぼ作り)が難しくなり、少しだけ早期退職をして実家に帰ってきたそうです。
そのきっかけは、帰省した時に年老いた両親が暗い部屋で二人とも黙って質素な昼食をとっていた光景を見たときに、「もう早く帰ってあげないと」と思ったからでした。
そして今、実家に帰って20年近くお米農家を続けてきたが、もう限界がきた。これからは草刈りと山の木の伐採(山林や田んぼをたくさん所有している農家でした)だけにしたいとお米つくりを辞める決断をされました。
● 体力の減退や高額な農業機械の買い替え・肥料代などの経費がかさむことで経営が成り立たないというのが表立った農家を辞めた理由。今は少ない年金と公民館の受付け係などの非常勤で得た収入でなんとか暮らしている。
● 数年前に「集落営農」の政策がすすめられたが、それは補助金により小さな農機具置き場はつくれたものの、農作業が軽減されたわけではなかった。70歳という年齢は集落の中で最も若かったので農作業量も増え、事務処理、会議内容の説明、みんなの意見のとりまとめ(高齢者な自分本位のことを主張するばかりで動くことはしない)などで益々精神的にも体力的にも負担が大きくなってしまった。
● 結局、超高齢化はますます進み、団体は解散しました。「田んぼ」は近隣の人に貸し出すことになりましたが、それを借りて耕作をしている人もまた高齢ですので限界が来ています。来年からまたこの一帯に耕作放棄地が増えます。
● なぜ米作にこだわるのか。田舎でもインターネット環境はケーブルテレビ回線の普及に伴って整ってきていますので、米作以外の農業がおこなわれている成功事例など、一部の農家さんは知っています。しかし高齢化と収益性、借入金の返済などを考えると現実的ではないのです。
もう半世紀以上も前から冬季の出稼ぎをしなくても暮らせるようにと、他の農作物生産を奨励し、補助金や指導も提供されていました。私の実家でも裏山を開墾して、夏ミカン畑を作っていたのですが、その開墾費用の一部は補助金が出ていました。しかし収支的には年間30万円にも満たなかったそうです。
約10年程度つづけたものの立ち行かなくなってやめざるを得なくなり、その果樹園だった山はヒノキが植えられています。その日の木も枝切り作業などができないまま生い茂っています。、国産ヒノキの価格は、一時的な高騰は過去にありましたが、現在は落ち着いています。ですからヒノキを切り出して運搬する費用を考えると赤字になります。
農家さんは一時的な農業振興政策の失敗事例が全国でたくさんあることも知っていますので、「思い切ってやってみよう」なんて気持ちにはなれないそうです。
● 高齢化は当たり前、暮らせないのですから。過疎地ですので若者が働く職場は限られています。どこの家庭も子供たちは全員出て行って親と同居している家庭はありません。実家の近くで働くのであれば、市役所や農協などが一番良い条件の就職口ですが、それを望む若者は少ないようです。実際、地元で就職をしている人からは「仕方なく地元で就職をしている」「都市部の大学等に行っていたが、都会にはなじめない」といった声を聴きます。
若者にとっては、こんな閉塞感が強く、やりたいことも見つからない田舎で暮らすなど考えられないことですし、親もまた子供に農業をさせたくないと思っています。街に出て働くことは当たり前のことです。
こんな話もう何十年も前から言われていることなので今更って感じなのですが・・・一方で田舎暮らしにあこがれ、それを実践している若者がいることも事実です。過疎地での若者の新しい生き方は人それぞれなのですが、主に農業収入で暮らしていくには、相当の工夫と努力、支援が必要になります。
「集落営農」政策はほとんど効果がなかった
集落単位での農業を推奨する「集落営農」の政策が本格的に始まったのは、2000年代以降です。これは、1999年に制定された食料・農業・農村基本法によって、農業の担い手育成が国の重要な課題として位置づけられたことが大きなきっかけとなりました。
集落営農の取り組みには、国や自治体から様々な補助金制度が設けられています。これらの補助金は、集落営農組織の設立から、その後の経営強化、法人化に至るまで、様々な段階で支援を行うことを目的としています。
しかし集落営農への政策支援は、高齢化と人手不足に悩む地域農業の救世主として期待されてきました。しかし、その実態は「税金の無駄遣い」と批判されるケースが少なくありません。
最大の課題は、組織化の弊害です。国の補助金を得るために形式的に集落営農組織を設立するだけで、実質的な経営改善や生産性の向上に繋がっていない事例が散見されます。 各農家が自分の農地を任せるものの、責任の所在が曖昧になり、意欲的な取り組みが生まれにくい構造になっています。
また、高額な農業機械を補助金で導入しても、使いこなせる人材が不足しているため、稼働率が低く、宝の持ち腐れになっているケースも多々あります。共同利用を巡る人間関係のトラブルも絶えず、かえって地域の対立を深める要因になることもあります。
結果として、集落営農は「農地を荒廃させない」ための一時的な延命措置にしかなっておらず、「儲かる農業」への転換には程遠いのが現状です。多額の税金が投入されながら、根本的な問題解決には至っていないこの状況は、抜本的な政策見直しを迫られています。
過疎化が進む日本の農村部において、農業の未来は明るくないと言われています。しかし、最近では「スマート農業」や「新規就農者」といった言葉が希望の光として語られることが増えました。
IT技術を導入し、意欲ある若者が農業に参入すれば、日本の農業はV字回復できる――そう考える人も少なくありません。しかし、現実はそれほど単純ではありません。ITの力と、農業に魅力を感じる若者の力だけでは、日本の農業の衰退を止めることはできないのです。
そして、農業政策が進まない最大の原因は、平坦で広い農地がない地域の小規模農家が大部分を占めているため、法人化して効率よく利益を上げることなど到底無理な話なのです。
また、もっと深い原因があります。終戦直後の日本で行われた、大地主から小作農に土地を分け与えた政策、農地改革です。これは、戦後の民主化政策の一環として、農村部の経済的・社会的不平等を解消し、日本の食料生産体制を安定させることを目的として、連合国軍総司令部(GHQ)の指令に基づいて実施されました。
それまで自分の土地を持たない小作農の人たちは大地主から譲り受けた自分の土地を守るために一生懸命働きました。今の高齢者たちはその親の苦労を見ていますので、おいそれとその小さい農地を手放すには抵抗があり、赤字を出してでも米作農業を続けなければという思いがあったようです。
若者の定着を阻む壁
若者が農業に魅力を感じて移住してきたとしても、彼らが直面する課題は山積しています。特に、農地の確保は大きな壁となります。耕作放棄地は増えていますが、所有権が複雑に入り組んでいたり、相続の問題で手がつけられなかったりするケースがほとんどです。意欲があっても、耕す土地が見つからなければ農業は始められません。
さらに、初期投資の高さも大きな負担となります。農業機械や施設、種苗など、新規就農には莫大な資金が必要です。国の補助金制度もありますが、それだけでは十分でないことも多く、自己資金や借金に頼らざるを得ないのが現状です。
流通と市場の構造的な問題
日本の農業が抱える問題は、生産現場だけではありません。流通と市場の構造そのものに、大きな課題があります。多くの農産物はJA(農業協同組合)や卸売市場を経由して消費者の手に届きますが、その過程で生産者の利益は目減りしてしまいます。
また、日本の農業は小規模農家が多く、価格競争力が低いという弱点があります。海外の安価な農産物との競争に晒され、価格を上げることができないため、いくら良いものを作っても十分な利益を得ることが難しいのです。
海外でお米を作るには問題点が多い
日本の農業法人が海外で米を生産している事例は、一般的にはあまり多く知られていません。その理由はいくつか考えられます。
まず、日本の農業法人が海外に進出する場合、米以外の作物(野菜や果物など)や、付加価値の高い加工食品の生産・販売に力を入れているケースが多いからです。これは、米は海外でも比較的安価に生産されているため、日本の法人が海外で生産しても、価格面で競争力を出すのが難しいという事情があります。
また、日本の米を海外に輸出する際、玄米で輸出し、現地で精米して販売するというビジネスモデルも存在します。これにより、消費者に「新鮮な日本米」として提供することができ、高付加価値化を図っています。この場合、海外で「生産」しているわけではありませんが、日本の農家と連携して海外市場を開拓していると言えます。
しかし、全くないわけではなく、個別の企業や個人が海外で米作りに挑戦している例は存在します。例えば、アメリカで日本の米作りに取り組み、高品質な米を生産している「田牧(タマキ)ファーム」の事例などが知られています。ただし、これらの事例は、日本の大手農業法人が大規模に海外展開しているというよりは、まだまだ特定の企業や個人の挑戦的な取り組みとして捉えるべきでしょう。
総じて、日本の農業法人の海外展開は、米の生産よりも、「日本ブランドの価値」を活かした高付加価値な農産物の生産や、流通・販売、あるいは農業技術の提供といった分野にシフトしている傾向が強いと言えます。
机上で作成される農業政策、そして国民の役割
当たり前すぎる農業政策については下記のとおりです。机上で作成すればこんな感じになるのですが、多くの過疎地の現状を見ると、あまりにも非現実的です。
- 農地の集約化と大規模化:耕作放棄地を有効活用し、意欲ある農家が大規模に農業を展開できるような仕組みを構築すること。
- 独自の流通ルートの開拓:インターネットなどを活用し、生産者が直接消費者に販売できる仕組みを強化すること。
- 付加価値の高い農業の推進:単なる農産物の生産だけでなく、加工品の開発や観光農業など、付加価値の高い事業を展開すること。
- 包括的な政策支援:単発的な補助金ではなく、新規就農者の育成から定着までを長期的にサポートする包括的な政策を打ち出すこと。
- ITと若者の力は、日本の農業を立て直すための重要なピースです。しかし、そのピースを活かすためには、国の政策、地域のコミュニティ、そして農家自身が一体となって、本質的な構造改革を進めることが不可欠なのです。
何より、これらの抜本的な改革を進めるためには、現実を知った政治家を輩出し、国民全体で政治を動かすことが不可欠です。ひと昔前まで農業従事者は農協組合員と同時に自動的に自由民主党員となっていました。今、当然のごとく農協離れ、自由民主党離れの流れがあります。冒頭で私が話を聞いた農家さんも、毎年耕作面積に応じた農薬や肥料を勝手においていく農協とは関わりたくないので、一切お米は供出しないと言われました。
最近SNSなどでカビの生えない薬品を付した輸入米のことが取り上げられています。消費者は、食の安全という観点からも単に価格の安さだけで農産物を選ぶのではなく、日本の農業を支えるという意識を持つことが重要です。また、一票の重みを理解し、農業政策を重視する政治家や政党に声を届ける必要があります。
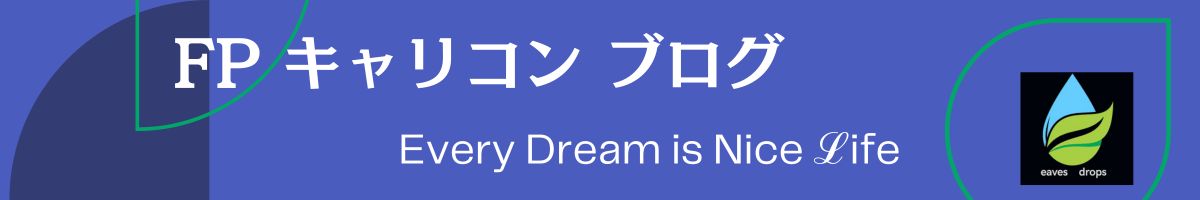

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/34188fb2.a725ab2f.34188fb3.ee3a5d32/?me_id=1213310&item_id=20007190&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3636%2F9784297113636.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント