以前、田舎暮らしの移住先を選ぶ際の条件として、交通の便、医療体制、買い物環境、インターネット回線など、様々な「必要条件」を語った記事を書きました。もちろん、生活の基盤を考える上で、それらは重要な要素でしょう。しかし、もしあなたが心の奥底で、そんな「常識」や「当たり前」といった枠組みを超えた、もっと根源的な何かを求めているのだとしたら?
今回のブログでは、あえてそうした条件に囚われない、魂の叫びに応えるような田舎暮らしの選択肢があるということをお伝えしたいと思います。
それは、利便性や効率性といった現代社会の価値観から少し距離を置き、もっとプリミティブな感覚、例えば、土の匂いや星の瞬き、風の音といった、私たちの中に眠る野生を目覚めさせるような暮らし方です。
スuマホの電波、コンビニの明かり、秒刻みの電車の ダイヤ、小集団内での同調強制の息苦しさ、私たちはいつの間にか、整然としたインフラと人間関係という名の檻の中で生きているのかもしれない。もちろん、その恩恵は大きい。しかし、時にはその便利さが、私たちから根源的な喜びや、忘れかけていた大切な感覚を奪っているのではないだろうか。
インフラ云々を飛び越え、あえて不便さの中に身を置く田舎暮らし。それは、失われた何かを取り戻す旅のようなものです。早朝、けたたましいアラームではなく、鳥のさえずりで目覚める。夜空を見上げれば、都会の光害とは無縁の、息をのむような満天の星が広がる。その光景は、人工的な光に慣れた私たちの魂を深く揺さぶる事でしょう。
蛇口をひねれば当たり前に出てくる水は、山から湧き出る清らかな恵みかもしれない。畑で育てたばかりの野菜は、土の香りをまとい、スーパーの画一的な野菜とは比べ物にならない力強い味わいを持つ。自分の手で何かを育てる喜び、自然の恵みを直接いただく豊かさは、お金では決して買えない。
もちろん、不便さもあるだろう。買い物に行くにも時間がかかるかもしれない。最新のエンターテイメントにすぐにアクセスできるわけではないかもしれない。しかし、その不便さこそが、私たちに大切なことを教えてくれる。本当に必要なものは何か、時間の流れをゆっくりと感じること、そして、自然のリズムに合わせた生き方。
そこで得られる心の充足感、自然との一体感、そして何よりも「生きている」という実感は、これまで私たちが追い求めてきた「便利さ」とは全く異なる種類の豊かさをもたらしてくれるはずです。
個の尊重と自然への回帰
それぞれの「個」を尊重し、自分らしい生き方を見つける。そして、時には自然の中に身を置いて、心と体をリフレッシュする。そんな生き方が、これからの私たちの社会にとって、より豊かな選択肢となっていくのかもしれません。
集団行動を好む傾向が強かった日本社会も、個人の多様な価値観が尊重される時代へと変化しています。ソロ活を楽しむ人もいれば、自然との共生を求めて田舎へ移住する人もいる。そして、その中には、私たちと同じように悩み、考え、新たな生き方を模索する著名人たちの姿もあります。
彼らの選択は、私たちに「本当に自分が大切にしたいものは何か」「どんな生き方が自分にとって心地良いのか」を改めて考えるきっかけを与えてくれます。
もしあなたが、日々の喧騒に疲れ、一人で過ごす静かな時間や、自然の中で心安らぐ時間を求めているなら、ソロ活をテーマにした作品や、著名人たちの田舎暮らしを描いた物語に触れてみてはいかがでしょうか。彼らの経験は、きっとあなたの背中をそっと押してくれるはずです。
個の時代を生きる私たちへ ~ソロ活、田舎暮らし、そして著名人たちの選択
かつて「和を以て貴しと為す」という言葉に象徴されるように、集団での行動を重んじる傾向が強かった日本社会。しかし、近年、その価値観は多様化し、一人で過ごす時間を積極的に楽しむ「ソロ活」や、自然との調和を求めて都市部を離れ田舎で暮らす人々が増えています。
満員電車に揺られ、オフィスで肩を寄せ合う毎日から解放され、自分のペースで過ごしたい。SNSの喧騒から離れ、静かな自然の中で自分と向き合いたい。そんな思いを抱く人が増えているのかもしれません。そして、意外なことに、私たちと同じように、あるいは私たちよりも早く、そんな生き方を選択している著名人たちがいるのです。
静かに自分と向き合う時間~ソロ活という選択~
一人カラオケ、一人焼肉、一人旅……かつては少し寂しいイメージもあった一人行動も、今や気兼ねなく自分の好きなように時間を使える自由なスタイルとして、多くの人に受け入れられています。
このソロ活をテーマにした作品も増えています。
少し古いのですがドラマ「おひとりさま」 (2009年 TBS系) は、恋愛よりも一人の時間を大切にするヒロイン(観月ありささん)の日常を描き、ソロ活の楽しさや奥深さをコミカルに表現しました。自分の好きなように過ごす時間の尊さ、そしてその中で見つけるささやかな幸せは、多くの共感を呼びました。
また、エッセイや指南書も多数出版されており、ソロ活を満喫するためのノウハウや心の持ちようが紹介されています。これらの書籍を読むと、一人でいることは決して孤独ではなく、むしろ自分自身と深く向き合い、内面を豊かにする貴重な時間なのだと気づかされます。
自然との共生を求めて~著名人たちの田舎暮らし~
著名人の中にも、そうした既存の価値観を飛び越え、自身の内なる声に従って田舎暮らしを選択した人々がいます。彼らの生き方は、私たちに新たな視点を与え、移住という選択肢の可能性を広げてくれるのではないでしょうか。
集団生活や都市部の利便性から離れ、自然豊かな場所で新たな生活を始める著名人たちは、私たちに「本当に豊かな暮らしとは何か」を問いかけているようです。
女優、歌手の柴咲コウさんは北海道に移住し、サステナブルな暮らしを実践しながら農業にも挑戦しています。YouTubeチャンネルでは、自然の中で生き生きと過ごす様子が公開され、多くの視聴者に影響を与えています。
柳葉敏郎さんは、お子さんの自然豊かな環境での子育てを願い秋田県に移住。地元の文化に触れながら、家族との時間を大切にしている様子が報じられています。
財前直見さんも、大分県でご家族と自然に囲まれた生活を送っており、畑での野菜作りを楽しむ様子がメディアで紹介されています。
彼らの選択は、必ずしも安易なものではないでしょう。利便性の低下や、地域社会との新たな関わりなど、都市部での生活とは異なる課題も存在するはずです。しかし、それでも彼らが自然との共生を選ぶのは、そこにかけがえのない価値を見出しているからに違いありません。
著名人の田舎暮らしを描いた作品たち
著名人の田舎暮らしは、ドラマや映画の題材としても魅力的に描かれています。
映画「WOOD JOB! (ウッジョブ) ~神去なあなあ日常~」 (2014年) は、ひょんなことから林業の世界に飛び込んだ若者が、厳しい自然の中で成長していく姿を描いています。都会の生活に馴染めなかった主人公が、自然の中で生きる喜びや厳しさを知り、自身の居場所を見つけていく物語は、田舎暮らしのリアルと魅力を伝えてくれます。
また、ドキュメンタリー番組などでは、著名人が田舎でどのような暮らしを送っているのか、その苦労や喜びが赤裸々に語られることもあります。彼らの経験を通して、田舎暮らしの理想と現実、そして本当に大切なものが見えてくるかもしれません。
日本の著者が書いた、実体験に基づいた田舎暮らしの本
- 「種まきノート – ちくちく、畑、ごはんの暮らし」 早川ユミ著: 布作家である著者が、高知の山奥で夫である陶芸家の小野哲平さんとともに、自然に寄り添いながら畑を耕し、季節の食材で料理をする暮らしを綴ったエッセイ。飾らない言葉で綴られた日常の中に、豊かな 暮らし のヒントが詰まっています。
種まきノート ちくちく、畑、ごはんの暮らし [ 早川ユミ ]
楽天で購入
- 「ぼくたちの古民家暮らし」 新田穂高著: 都会育ちの著者が、田舎の古民家を購入し、DIYで改修しながら自然と共に暮らす日々を綴ったエッセイ。古民家の魅力や改修の苦労、地域の人々との交流などがユーモラスに描かれています。
・「中年女子、ひとりで移住してみました: 仕事・家・暮らし 無理しすぎない田舎暮らしのコツ」 鈴木みき著: 都会で働く中年女性が、ひょんなことから田舎へ移住し、仕事や住まい、人間関係など、様々な壁にぶつかりながらも自分らしい暮らしを ধীরে ধীরে 築いていく様子を綴った実体験に基づいたエッセイ。移住のリアルな側面と、前向きな姿勢が共感を呼びます。
中年女子、ひとりで移住してみました 仕事・家・暮らし 無理しすぎない田舎暮らしのコツ [ 鈴木 みき ]- 「ベニシアのハーブ便り 京都・大原の古民家暮らし」 ベニシア・スタンリー・スミス著: イギリス出身の著者が、京都の大原で古民家を再生し、ハーブを育てながら自然と調和した暮らしを送る様子を綴ったエッセイ。美しい写真とともに、季節の移ろいや手作りの生活の温かさが伝わってきます。
- 北アルプス・黒部源流の山小屋、薬師沢小屋で働くイラストレーターのやまとけいこさんが送る、山小屋の厨房が舞台のエッセイ集!
- 「寒山の森から」 椎名誠著: 作家である著者が、長年暮らす房総の森での生活や、自然観察、釣り、狩猟などを通して感じる自然の豊かさや厳しさを綴ったエッセイ。自然の中に身を置くことの喜びや、自然との深い繋がりを感じさせます。
これらの本は、著者が実際に田舎で生活した経験に基づいているため、その土地のリアルな暮らしや、著者の喜びや苦労が伝わってきます。移住を検討されている方はもちろん、田舎暮らしに興味がある方にもおすすめです。ぜひ手に取って、それぞれの著者の 暮らしを垣間見てみてください。
実体験に基づいた外国人の田舎暮らしを紹介する本
- The Only Gaijin in the Village: A Year Living in Rural Japan」 イアン・マロニー著(日本語訳版タイトル:「村にたった一人の外国人 愉快な日本の田舎暮らし」 小学館文庫)
- スコットランド人作家であるイアン・マロニーさんが、日本の過疎化が進む小さな村に1年間住んだ体験を綴ったエッセイです。文化の違い、言葉の壁、そして温かい村人たちとの交流を通して、日本の田舎の魅力や課題をユーモラスかつ鋭い視点で描いています。外国人ならではの発見や驚きが満載で、日本の田舎を再発見できるかもしれません。
- アレックス・カー著(日本語訳版タイトル:「犬と鬼とワサビ畑―失われたアメリカの辺境を求めて」 角川文庫)
- アメリカ人である著者が、日本の山奥の限界集落に移住し、古民家を再生しながら地域の人々と交流する様子を描いたノンフィクションです。日本の伝統文化や自然の美しさ、そして過疎化という現実の中で生きる人々の姿を、深い洞察力とユーモアを交えて描いています。
- 「外国人が熱狂するクールな田舎の作り方」 山田拓著(新潮新書)
- 世界80カ国を旅した経験を持つ著者が、岐阜県飛騨市の古川という小さな町で、外国人観光客を惹きつける独自の観光戦略を展開し、地域を活性化させた実体験を綴ったノンフィクションです。「何もない田舎の日常」を魅力として発掘し、外国人ならではの視点で日本の田舎の価値を再発見する過程が描かれています。
- 「ボクのニッポン漂流記」 ポール・グリーンバーグ著(日本語訳版タイトル:「ボクのニッポン漂流記 – サムライ、ゲイシャ、そして奇妙なサイダー」 角川文庫)
- アメリカ人ジャーナリストである著者が、日本の様々な地域を旅し、そこで出会った人々や文化、そして自身の体験を綴った紀行記です。その中で、日本の田舎での人々の温かさや、都会とは異なる時間の流れ、独特の文化に触れる様子が描かれています。ユーモラスな視点と深い洞察力で、日本の魅力を再発見させてくれる一冊です。
これらの本は、それぞれ異なる視点から日本の田舎暮らしの様子を描いており、外国人ならではの発見や、日本人が気づかない日本の魅力に触れることができるでしょう。
- 「A Year in Provence」 ピーター・メイル著
- 南フランスのプロヴァンス地方に移住したイギリス人夫婦の1年間の生活を描いた、世界的に有名なエッセイです。美しい風景、美味しい食べ物、そして個性的な地元の人々との交流が、ユーモラスな筆致で綴られています。
- 「Driving Over Lemons: An Optimist in Andalucia」 クリス・スチュワート著
- スペインのアンダルシア地方の山奥にある農場を購入し、そこで生活を始めたイギリス人男性の体験記です。農業の苦労や喜び、地元の文化、そして個性豊かな隣人たちとの交流が、明るくユーモラスに描かれています。続編もいくつか出版されています。
- スペインのアンダルシア地方の山奥にある農場を購入し、そこで生活を始めたイギリス人男性の体験記です。農業の苦労や喜び、地元の文化、そして個性豊かな隣人たちとの交流が、明るくユーモラスに描かれています。続編もいくつか出版されています。
「Under the Tuscan Sun」 フランシス・メイエス著
- 離婚を機に、衝動的にイタリア・トスカーナ地方の古い別荘を購入し、改修しながら生活を始めたアメリカ人女性の回顧録です。美しい風景の中で、新しい生活を築き、自分自身を再発見していく過程が描かれています。後に映画化もされました。
「Our Ecuador Retirement: The First 8 Months」 ドナルド・マレー著
- 退職後にエクアドルに移住したアメリカ人夫婦の最初の8ヶ月間の体験記です。文化、気候、生活習慣の違い、そして新しい生活への適応などが率直に語られています。
これらの本は、単なる旅行記ではなく、実際に外国の田舎で生活した著者の実体験に基づいているため、その土地の文化、人々、そして生活のリアルな側面を知ることができます。移住を検討されている方はもちろん、海外の田舎暮らしに興味がある方にもおすすめです。
インフラという名のレールから降り、自分の足で大地を踏みしめる生き方。それは、不便さの中にこそ見出すことのできる、かけがえのない豊かさに満ちている。田舎暮らしは、私たちに、人間本来の生きる力を呼び覚まし、真の幸福とは何かを教えてくれるでしょう。
にほんブログ村
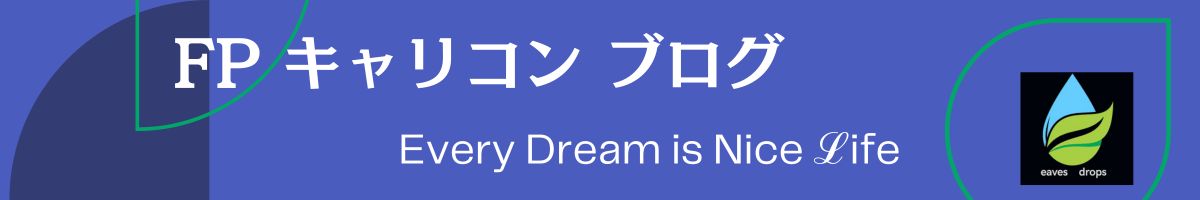



コメント