最近、「プラチナNISA」という言葉を耳にした方もいらっしゃるかもしれません。これは、政府が検討している、主に高齢者世代向けの新しいNISA(少額投資非課税制度)の愛称のようなものです。
「プラチナNISA」って何?
現行のNISA制度は、若い世代を中心に、コツコツと資産を増やしていくのに適した制度です。しかし、「毎月、少しでも収入があると安心だ」と感じる私たち高齢者世代のニーズには、必ずしも合致しない部分もあります。
そこで検討されているのが「プラチナNISA」です。これは、主に65歳以上の方を対象に、以下のような特徴を持つNISAになることが考えられています(まだ正式に決まったわけではありません)。
ポイント(検討段階):
毎月分配型投資信託も対象に? これまでのNISAでは、長期的な資産形成には向かないとされてきた「毎月分配型投資信託」が、プラチナNISAでは対象になる可能性があります。「毎月、定期的に収入を得たい」という私たちのニーズに寄り添った制度設計が検討されているのです。
分配型投資信託とは、運用で得た収益の一部を、定期的に(毎月、四半期ごとなど)投資家へ分配金として支払うタイプの投資信託です。ただし 毎月分配金は、運用で得た利益だけでなく、私たちの元本を取り崩して支払われている場合もあります。特に運用成績が良くない時期には、分配金の多くが元本から支払われている可能性があります。
非課税投資枠は? 年間に投資できる金額や、生涯にわたって非課税で保有できる金額は、現行のNISAとは異なる設定になるかもしれません。
対象年齢は? 原則として65歳以上の方が対象となる見込みです。
なぜ「プラチナNISA」が検討されているの?
背景には、私たちが長年かけて築き上げてきた大切な資産を、より有効に活用してほしいという国の思いがあります。「貯蓄から投資へ」の流れを促し、私たちの生活を少しでも豊かにすることを目指しているとのことです。
分配型投信と「プラチナNISA」の組み合わせ:メリット
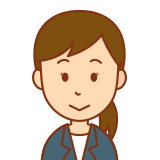
メリットについては、サラッと読んでくださいね。 大事なのは次の項目のデメリットの方です。
もし「プラチナNISA」で毎月分配型投資信託が対象となれば、私たちにとって以下のようなメリットが考えられます。
- 毎月のお小遣いが増えるかも: 投資によって得た利益から、毎月分配金を受け取れる可能性があります。これが非課税になることで、手元に残るお金が増え、生活にゆとりが生まれるかもしれません。
- 資産を取り崩す心理的な負担が減るかも: 大切な貯金を少しずつ使うことに抵抗がある方もいらっしゃるかもしれません。毎月分配金という形で「運用益」を受け取る感覚になれば、心理的な負担が軽減される可能性があります。
- 投資の成果が分かりやすいかも: 毎月分配金を受け取ることで、「投資をしていて良かった」と実感しやすくなるかもしれません。
分配型投信と「プラチナNISA」の組み合わせ:デメリット(注意点!)
しかし、良いことばかりではありません。毎月分配型投資信託と「プラチナNISA」の組み合わせには、注意しておきたいデメリットもあります。
- 元本が減ってしまう可能性も: 毎月分配金は、運用で得た利益だけでなく、私たちの元本を取り崩して支払われている場合もあります。特に運用成績が良くない時期には、分配金の多くが元本から支払われている可能性があることを理解しておきましょう。NISAで非課税になるのは、あくまで利益に対してです。元本が減ってしまうのは、私たちにとって大きなマイナスです。
- お金が増えるスピードが遅くなるかも: 本来であれば、得た利益を再び投資に回すことで、さらに資産を増やしていく「複利」という効果が期待できます。しかし、毎月分配金を受け取ってしまうと、この複利の効果が小さくなってしまう可能性があります。
- 手数料が高い場合も: 毎月分配型の投資信託は、一般的に運用にかかる手数料が高めに設定されている傾向があります。
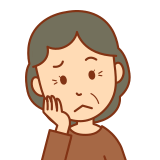
せっかく非課税になっても、高い手数料で利益が目減りしてしまう可能性だってあるんですね。
- 投資のリスクを忘れずに: 毎月分配金があるからといって、投資にリスクがないわけではありません。市場の状況によっては、投資したお金が減ってしまう可能性も十分にあります。
- 成長のチャンスを逃すかも: もし「プラチナNISA」の非課税枠が、成長が期待できる株式などに投資できる現行のNISA(成長投資枠)よりも小さい場合や、毎月分配型に特化している場合、将来的に資産を大きく増やすチャンスを逃してしまうかもしれません。
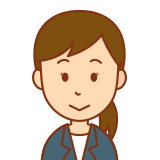
NISAは非課税という大きなメリットがある一方で、税金面でのデメリットもいくつか存在します。簡単にまとめると以下のようになります。
- 損益通算ができない: NISA口座内で損失が出た場合、その損失を他の課税口座の利益と相殺(損益通算)することができません。課税口座であれば、損失が出た場合に他の利益と相殺して税金を抑えることができますが、NISA口座ではそれができません。
- 損失の繰越控除ができない: NISA口座で損失が出ても、その損失を翌年以降に繰り越して、将来の利益と相殺することもできません。課税口座であれば、損失を最大3年間繰り越して控除することができます。
- 非課税投資枠を超えた部分は課税対象: 年間の投資上限額(つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円)や生涯非課税保有限度額(1800万円)を超えて投資した部分は、通常の課税口座と同様に課税されます。非課税の恩恵を受けられるのは、あくまで枠内での投資に限られます。
- 課税口座との柔軟な資金移動ができない: 一度NISA口座に入金した資金や、NISA口座で購入した金融商品を、税制上のメリットを受けながら課税口座に移管することは基本的にできません。移管する場合は、一度売却して現金化し、改めて課税口座で買い直す必要があります。その際、売却益が出れば課税されます。
これらのデメリットを理解した上で、NISAのメリットを最大限に活かすためには、非課税投資枠を有効活用し、長期的な視点で運用することが重要となります。
NISAの税金面でのデメリットについてはこちらもクリックして、ご覧ください。
大切なこと:焦らず、 十分に 理解すること
「プラチナNISA」は、まだ検討段階の制度です。もし導入されたとしても、毎月分配型投資信託との組み合わせが良いとは限りません。
大切なのは、焦って判断するのではなく、制度の内容や、毎月分配型投資信託の仕組み、メリットとデメリットをしっかりと理解することです。
ご自身の 経済的な状況や、 投資の目標に合わせて、どのような方法が最適なのかを慎重に検討しましょう。もし不安なことがあれば、銀行や証券会社の窓口よりも、信頼できる ファイナンシャルプランナーなどに相談することも考えてみてください。
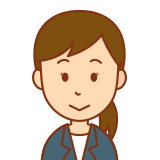
銀行や証券会社の窓口は、自社の商品を販売することが主な目的の場合があります。新金融商品の場合、金融庁の指導により金融機関は販売強化をする必要があります。一方、独立系のファイナンシャルプランナー(FP)は、特定の金融機関に属さず、中立的な立場から、あなたの個別の状況や目標に合わせたファイナンシャルプランを提案してくれる可能性が高いと言えます。
最後に
シニア世代にとって、大切な老後資金を守り、賢く活用していくことが何よりも重要です。ますます政府や財務省は国民の金融財産を吸い上げるような施策を打って出る可能性があります。
金融庁はかつて、毎月分配型などの「分配型投資信託」が、顧客の長期的な資産形成に必ずしも資さないとして、その販売姿勢に警鐘を鳴らし、販売の萎縮を促すような動きがありました。
なぜ高齢者向けに「プラチナNISA」として政府が検討しているのか、しっかりと考えていただいた方が良いと思います。
冷静な判断を心がけていきましょう
⇓ クリックをお願いします。
にほんブログ村
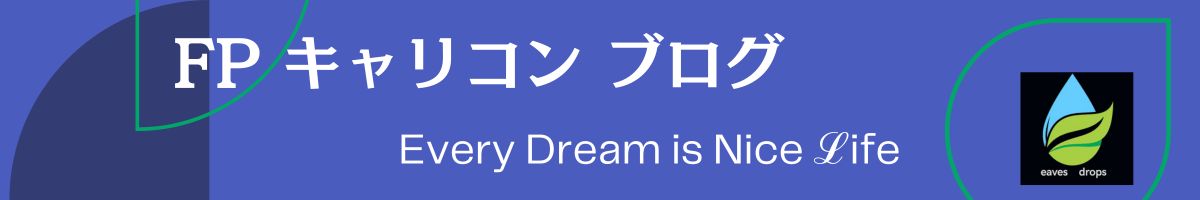

コメント