科学や物理学の進歩は目覚ましいものがあります。スマートフォン一つで地球の裏側と瞬時につながり、かつては想像もできなかった技術が現実の生活を変えています。しかし、その技術的な「進歩」とは裏腹に、私たち人間の暮らしの質、特に人間関係や社会の安定性は、まるで反比例するように悪化の一途を辿っているように見えます。
世界を見れば、貧困と格差は広がり続け、地域紛争や戦争の火種は絶えません。国内でも、人間関係の希薄化、孤独死の増加、そして将来への漠然とした不安が蔓延しています。なぜ、これほどまでに豊かな知恵と技術を持ちながら、私たちは互いを傷つけ合い、分断された社会で生きることを強いられているのでしょうか。
科学を超える「人間の壁」の正体
その原因は、科学技術では解決できない、より根深い人間の本質にあります。
- お金と欲望の暴走: 経済活動を動かす「お金」というツールは、無限の人間の欲望と結びつくことで、格差を固定化し、社会を分断する主要因となりました。
- 価値観の断絶: グローバル化と多様化が進む中で、宗教や文化、一人ひとりの価値観の違いは、相互理解の材料になるどころか、対立を深める燃料となっています。
私たちは、これらの「人間の壁」を、表面的な**「優しさ」や「親切」という仮面**で覆い隠してきました。
偽善の仮面を脱ぐ勇気
特に日本社会において、「優しさと親切」という建前は、本音の貪欲さや利己的な行動を隠すための便利な道具になっていないでしょうか。
山口県の田舎のような共同体の濃い地域に住んでいると、その違和感を強く感じます。地域や組織の集まりで表面上は和やかに振る舞いながら、その裏では、自分や属する組織、家族だけが「得」をすることに優越感を覚え、他者の犠牲には無関心でいる—そんな二重の感情を抱える人々が多くいます。
貧困や格差が拡大する原因を、「政治屋のせいだ」「社会の構造が悪い」と無責任な他人事として語る人が多いのは、まさにこの偽善の表れです。自分自身が、その格差を享受し、あるいは黙認することで、体制の一部となっていることに目を向けようとしないのです。
第一の目標:「暮らしやすさ」の正直な探求
もう、建前で互いを傷つけ合うのはやめにしませんか。私たちは、そろそろ「優しくて親切な日本人」という仮面を取り払い、正直に自分と家族の「暮らしやすさ」を探求することを第一の目標にすべきです。
暮らしやすさとは、単に経済的な豊かさだけではありません。それは、不必要なストレスがないこと、自分の意見が正直に言えること、そして他者の目を気にしなくて済む社会です。
その第一歩は、「自分は得をしたいと思っている」「自分の家族が一番大事だ」という、誰もが持つ利己的な本音を認めることから始まります。その正直さを土台にして初めて、私たちは真に持続可能で、互いに許容し合える社会の仕組みを、冷静かつ合理的に構築できるのではないでしょうか。
私たちが本当に進歩すべきは、宇宙の彼方ではなく、人間の心と社会の仕組みです。
心理学者のとらえ方
現代社会に見られるような「技術の進歩と人間関係の悪化の反比例」や「表向きの親切と裏腹の利己心」といった傾向について、心理学者は深く掘り下げて分析しています。これは主に、進化心理学、社会心理学、そして自己心理学の観点から捉えられます。
以下に、主要な心理学的概念と、その人間関係への適用例を挙げます。
1. 進化心理学:利己的な遺伝子と限定された協調性
進化心理学は、人間の行動や感情の多くが、遺伝子を存続させるための適応戦略に基づいていると捉えます。
概念:包括的適応度(Inclusive Fitness)
- 捉え方: 人間が本質的に持っている「利己的な傾向」は、自分の遺伝子(または血縁者の遺伝子)を後世に残すという生物学的な動機に基づいています。で前述で指摘された「自分や属する組織、家族が得をしていくことに優越感を覚える」という心理は、この包括的適応度を高めるための本能的なプログラムと解釈できます。
- 人間関係への適用: 協力や親切(利他行動)は、「互恵的利他主義」、つまり「将来、自分に利益が返ってくるだろう」という期待や、「内集団」(家族、組織、地域)の生存に役立つ場合に限定されます。「優しさ」の仮面は、集団内の調和を保ち、資源配分における自分の立場を守るための洗練された戦略であり、本質的な利他心ではないと見なされます。
2. 社会心理学:認知的不協和と道徳的ライセンス
社会心理学は、個人が社会集団の中でどのように自己を正当化し、振る舞うかを分析します。
概念:認知的不協和(Cognitive Dissonance)
- 捉え方: 人間は、自分の行動と信念(価値観)が矛盾する状態(不協和)を嫌い、それを解消しようとします。
- 例:「私は優しくて親切な人間でなければならない(信念)」 vs. 「私は自分の組織が得をするように裏で画策している(行動)」。
- 人間関係への適用: 前述で指摘された「表面上は優しさを取り繕っている」状態は、この不協和を避けるために生じます。人々は、自分の利己的な行動を正当化するために、「これは組織のためだ」「誰もがやっていることだ」といった理由を探し、偽善的な振る舞いを無意識のうちに合理化します。
概念:道徳的ライセンス(Moral Licensing)
- 捉え方: 過去に道徳的な行為(例:慈善活動に参加、表面的な親切)を行ったという実績があると、その後の非倫理的な行動を自分に許可してしまう心理的傾向です。
- 人間関係への適用: 「私は普段から親切にしている」という意識が、「だから、今回は自分の利益を優先しても許される」という**「免罪符」**になり、裏表のある利己的な行動を強化してしまう可能性があります。
3. 自己心理学:承認欲求と社会的比較
現代社会のストレスや競争は、個人の自己認識と他者との比較に影響を与えます。
概念:社会的比較理論(Social Comparison Theory)
- 捉え方: 人間は、自分の価値や能力を評価するために、他者と自分を比較します。
- 上向き比較(Upward Comparison): 自分より優れている人と比較し、優越感を得る(「得をする」ことに優越感を覚える動機)。上向き比較は、人間が自己評価を行う上で自然に行う基本的な認知プロセスの一つですが、その結果がポジティブになるかネガティブになるかは、その人の自己効力感(自分はやれるという感覚)や、比較対象との心理的な距離に大きく左右されます。
- 人間関係への適用: 現代の格差社会では、常に他者との比較が行われ、「成功=資源や優位性を獲得した状態」と定義されがちです。これにより、個人は競争心を剥き出しにし、自分の優位性(=他者の劣位)を確認することを自己の価値に結びつけます。「自分や家族が得をする」ことは、この競争社会における成功の証明となり、その優越感が偽善的な振る舞いの原動力となり得ます。
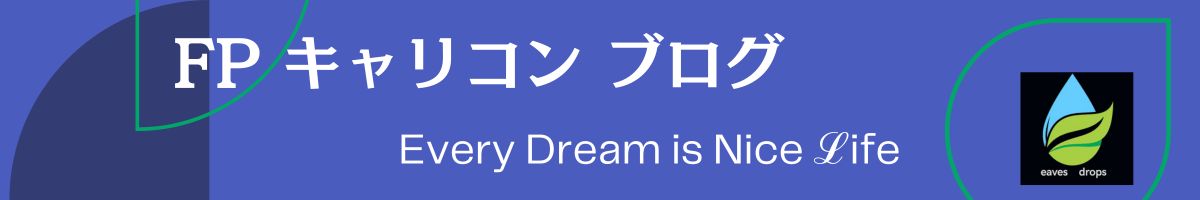
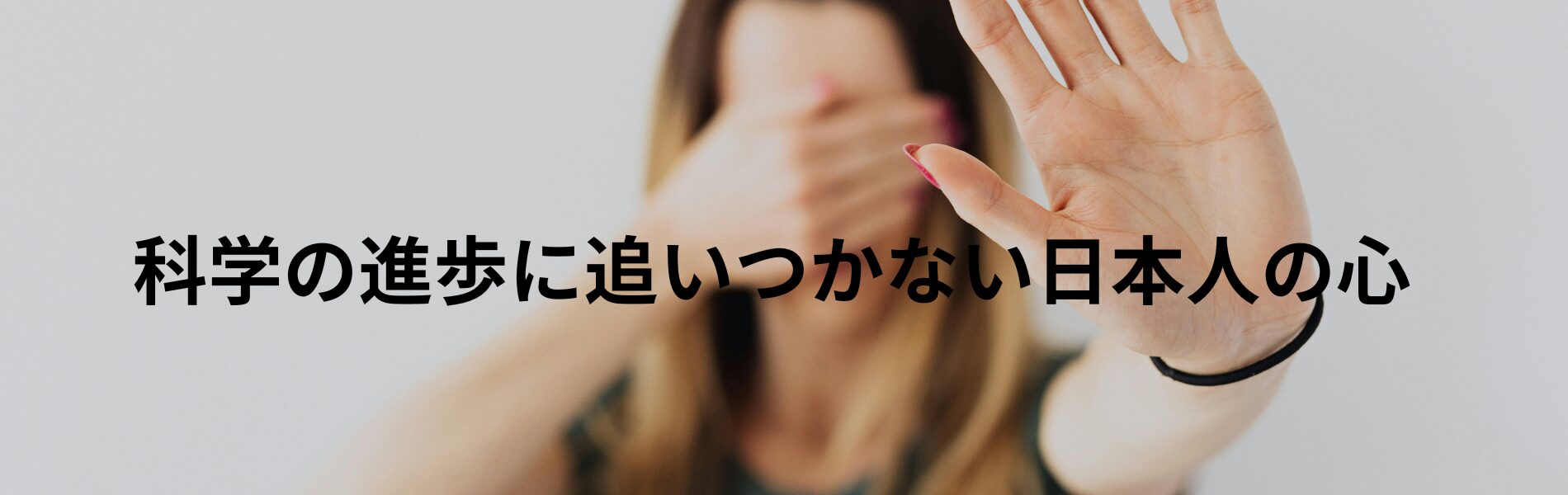
コメント