山口県では先の参議院選挙で、当然のように与党議員が当選されました。しかし、私が最近接した65歳以上の高齢者の方々の中には、「自民党一辺倒」から「野党議員を増やさないと」と今までとは違った意見を言われる人が半数近くいらっしゃいました。
新しい政党議員や著名人たちの政府に批判的なSNS等の配信をよく見ている人、そうでない人に関わらずです。
普通に苦しい家計
生活の中で家計が苦しくなっていることをヒシと実感されています。ある69歳の女性は8月支給の年金額振込通知書を見せながら話してくれました。
2か月分の支給額14万5千円、介護保険料が2万4600円、差し引き12万600円です。ひと月約6万円での生活になります。「お盆には孫たちが来るので、スイカやおいしい肉を思いっきり食べさせてやりたいけど、スイカひと玉3千500円以上もするし・・・お盆が過ぎたらまた私はそうめんの毎日だね」って笑いながら話してくれました。
年齢が60代~70代の人たちの多くは、今までそれほど生活苦を実感しなくてもよかったのかもしれません。もちろん子供の教育費や住宅ローンなどで贅沢はできなかったのですが、それでも今の厳しい家計での暮らしぶりは想定外でしょう。
【コミュファ光】超高速インターネットが1年間ずっと月額980円〜!
政治のせいにはしたくないけど、やはり政治家の老害じゃないかな
年齢だけで「政治家の老害」と決めつけるのは間違っていますが、いま国民の政治不信と生活に苦しんでいる現状を見ると、無関係とはいえません。
また、高齢ではなくてもその配下に入って保身を保つ政治家もいるようですし、地元の老害政治家を取り巻く支援者の中にも老害があります。
政治家の「老害」とは、主に以下の3つの意味合いで使われます。
1. 権力にしがみつくこと
長期間にわたり権力を独占し、若手議員への世代交代を妨げている状態を指します。自身の政治的な立場や利権を守るために、新しい風を入れず、組織の活性化を阻害していると批判されます。
2. 時代遅れの政策や価値観
古い時代に形成された価値観や成功体験に固執し、現代社会の課題や変化に対応できない状態を指します。具体的には、デジタル化の遅れやジェンダー問題への理解不足などとして現れます。
3. 利己的な行動
国民全体のためではなく、自身の出身団体や特定支持層、あるいは個人的な利益のために政治を行うことを指します。特に、引退を目前とした政治家が、自身の功績を残すために不必要な公共事業や法案を強行するケースなどが含まれます。
これらの行動は、政治の停滞や国民の不信感につながるため、「老害」という言葉で批判されることがあります。
「政治家の老害」が批判されるのは、国民や社会全体の利益よりも、自身の政治的地位、名誉、あるいは特定の利権を守ろうとすることにあります。これはまさに保身そのものです。
具体的には、以下のような共通点が見られます。
- 現状維持: 変化を嫌い、自身の地位が脅かされるような新しい政策や人材の登用を避ける。
- 責任転嫁: 自身の失敗や不都合な事実を認めず、責任を他者に押し付ける。
- 利己的な行動: 国民のためと謳いながら、実際には自身の政治基盤を固めるための行動をとる。
このように、「政治家の老害」は、保身という概念が政治の世界で具体的な形で現れたものと考えることができます。
政治家の老害を根絶する方法
政治家の「老害」を根絶する特効薬はありませんが、以下の方法が世代交代や組織の活性化に繋がる可能性があります。
1. 議員の任期や年齢制限の導入
法律で国会議員の連続当選回数や立候補できる年齢に上限を設けることで、強制的に世代交代を促す方法です。これにより、長期的な権力独占を防ぎ、若い世代に政治の舞台を提供できます。
しかし、法律で国会議員の連続当選回数や年齢に上限を設けることは、すでに権力を持っている「老害」とされる議員自身が決定権を持っているため、現実的には極めて困難です。
この難問を解決するために、以下のような別の視点や方法が考えられます。
1. 国民世論の力
国民の強い世論が形成されれば、政治家も無視できなくなります。選挙で「世代交代」を掲げる政党や候補者が躍進したり、SNSなどで有権者の声が可視化されたりすることで、間接的に圧力をかけることができます。
2. 政党内の自主的なルール
政党が自らの規約として、役員の任期や候補者の年齢に制限を設ける方法です。これは、法律のように強制力はありませんが、国民に「この政党は世代交代に積極的だ」というイメージを与えることができます。
3. 憲法改正
憲法改正の議論の中で、国会議員の任期や年齢制限について議論する方法です。これは非常にハードルが高いですが、国会ではなく国民投票で最終的な是非が問われるため、老害議員の抵抗を乗り越える可能性があります。
4. 権力移譲を促す仕組み
若手議員が育つような、権力移譲を促す仕組みを導入する方法です。例えば、委員会などで若手議員に重要な役職を任せたり、ベテラン議員が引退後も経験を活かせるような相談役制度を設けたりする方法が考えられます。
これらの方法は、すべてに共通して言えることですが、短期間で解決できるものではありません。しかし、地道な国民の意思表示や、政党内の意識改革が、長期的に権力にしがみつく老害議員を減らすことに繋がる可能性があります。
2. 若者世代の政治参加の促進
若者の投票率向上や政治への関心を高めることが重要です。具体的には、若者が投票しやすいオンライン投票の導入や、若者向けの政治教育を充実させるなどの対策が考えられます。若者の意見が政治に反映されやすくなれば、高齢世代の議員も若者のニーズを無視できなくなり、世代間のバランスがとれた政策が生まれやすくなります。
3. 政党内の人事刷新と透明化
各政党が、党首や幹部役員の任期を明確に定め、世代交代を定期的に行うことが有効です。また、候補者選定の基準を明確にし、透明性を高めることで、一部の古参議員の意向に左右されない公正な人事が行われるようにするのも一つの方法です。
権力移譲、身を引く正義感を心理学で説明
心理学において、「権力移譲」や「身を引く正義感」は、権力が個人に与える影響と自己のアイデンティティとの関係性という観点から説明できます。
権力移譲の心理学
権力を持つと、人はその権力を手放すことを極端に嫌う傾向があります。この心理は、以下の要素が複合的に絡み合って生じます。
- 自己アイデンティティとの同一化: 長く権力の座にいると、その地位や役割が自己のアイデンティティと強く結びついてしまいます。権力を失うことは、自己の存在価値そのものが失われるという脅威に感じられます。
- 認知バイアス: 権力を持つと、自分の判断や行動は常に正しいという「正当化バイアス」が強まります。そのため、自身の時代遅れの考えや間違った判断を認められず、外部からの批判や新しい意見を無視するようになります。
- 社会的勢力感: 権力を持つことで、自分の影響力が過大評価され、他者への共感能力が低下することが心理学的に示唆されています。これにより、権力移譲の必要性や、後進が抱える困難への理解が難しくなります。
「身を引く正義感」の心理学
「身を引く正義感」という概念は、心理学では直接的に研究されているわけではありませんが、自己の正義感が内面的な満足感と結びつく現象として解釈できます。
- 自己肯定感の充足: 「身を引く」という行為は、一見すると敗北のように見えますが、自身の価値観や信念(正義感)を貫くことによって、内面的な自己肯定感を得る行為でもあります。自己の尊厳を守るために、物理的な権力や地位を放棄する選択をするのです。
- 承認欲求からの解放: 外部からの承認や評価に依存するのではなく、「正しいことをした」という自己評価を優先する心理状態です。この段階に至ると、他者からの批判や、権力を失うことへの恐怖を乗り越えやすくなります。
「身を引く正義感」は、権力にしがみつく心理とは対照的な、より高い次元の自己コントロールの表れと言えるでしょう。権力から来る外部的な満足よりも、信念に基づいた内面的な満足を追求する心理的成熟を示す行為です。
老害と戦後の義務教育の関係性は
老害」と戦後の義務教育は直接的な因果関係で結びつけられるものではありませんが、特定の世代の価値観形成という点で関連性があると考えられます。
戦後教育の理念と「老害」の価値観
戦後の義務教育は、軍国主義教育を否定し、個人の尊厳、民主主義、そして平和国家の形成者を育てることを理念として始まりました。特に、団塊の世代は、この新しい教育制度のもとで育った最初の世代です。
この世代の価値観には、以下のような特徴が見られます。
- 勤勉・目標達成志向: 高度経済成長期に社会に出たため、「努力すれば報われる」「目標に向かって邁進すれば成果はついてくる」という成功体験を強く持っています。
- 組織への忠誠: 終身雇用や年功序列といった制度の中でキャリアを築いたため、会社や組織への帰属意識が強く、そのルールや慣習を重んじる傾向があります。
- 民主的解決志向: 民主主義を学び、話し合いによる問題解決を重視する姿勢を持っています。
理念と現実のギャップ
これらの価値観は、本来はポジティブな側面を持つものです。しかし、時代が変化し、新しい価値観や技術が台頭する中で、過去の成功体験や古い慣習に固執すると、それが「老害」と見なされるようになります。
たとえば、年功序列を前提とした組織のルールや、長時間労働を美徳とする考え方は、多様性や個人の幸福を重視する現代社会の価値観と衝突します。その結果、「昔はこうだった」と自分の経験を押し付けたり、新しいやり方を否定したりする行動が、若者から「老害」と批判される要因となるのです。
つまり、戦後の義務教育そのものが「老害」を生み出したわけではなく、その教育を受けた世代が、時代の変化に価値観をアップデートできなかったことが、「老害」という問題意識に繋がっていると言えるでしょう。
若者が作る新しい政治団体、理念に賛同する高齢者がなすべきこと
高齢者が若者の新しい政治団体を支持している事実を若者に理解してもらうには、いくつかの効果的な方法があります。大切なのは、単に「わかってほしい」と主張するだけでなく、若者が共感しやすい形やチャネルで情報を届けることです。
1. 共有の目標と価値観を強調する
高齢者がなぜこの新しい政治団体に賛同しているのか、その理由を具体的に伝えることが重要です。
- 「過去の反省」を語る: 高齢者自身の過去の政治に対する不満や、失敗から学んだことを率直に語ることで、若者との間に信頼関係を築くことができます。「昔、自分たちができなかったことを、君たちには実現してほしい」というメッセージは、若者の共感を呼びやすいでしょう。
- 「未来への希望」を共有する: 団体の掲げる理念が、高齢者自身の未来だけでなく、孫や次の世代の未来をどう変えるのかを具体的に語ります。「環境問題」「社会保障の持続可能性」といった、世代を超えて共有できる課題を強調することで、共通の目標意識を持ってもらえます。
2. 多様なコミュニケーションチャネルを活用する
若者が日常的に利用するメディアやプラットフォームを通じて、情報を発信します。
- SNS(X, TikTok, Instagramなど)での発信: 短い動画やインフォグラフィックを用いて、高齢者と若者が対話する様子を配信します。例えば、高齢者が団体の理念を簡潔に説明したり、若者の質問に答えたりするコンテンツは、視覚的にもわかりやすく、拡散されやすいです。
- 共同イベントの開催: 地域の清掃活動やボランティア活動など、政治活動ではない共同イベントを開催します。世代を超えて一緒に汗を流すことで、言葉だけでは伝わらない信頼関係を築くことができます。
- メディアの活用: 若者向けのオンラインメディアやポッドキャストに、高齢者の支持者がゲストとして出演し、自らの言葉で理念を語ってもらうことも有効です。
3. 具体的な「行動」を見せる
言葉だけでなく、具体的な行動を通じて誠意を示します。
- 寄付やボランティア活動への参加: 理念への賛同が単なる口先だけのものでないことを示すために、高齢者からの寄付やボランティア活動への積極的な参加を可視化します
。 - 若者の意見を尊重する姿勢: 団体の意思決定プロセスにおいて、若者の意見が真摯に受け止められていることを示す。高齢者の支持者も若者の意見に耳を傾ける姿勢を明確にすることで、若者は自分たちが「利用されている」のではなく、「共に歩んでいる」と感じることができます。
これらの方法を組み合わせることで、高齢者の支持が単なる「同情」や「お涙頂戴」ではなく、共通の未来を創るための真剣な行動であることを、若者に伝えることができるでしょう。
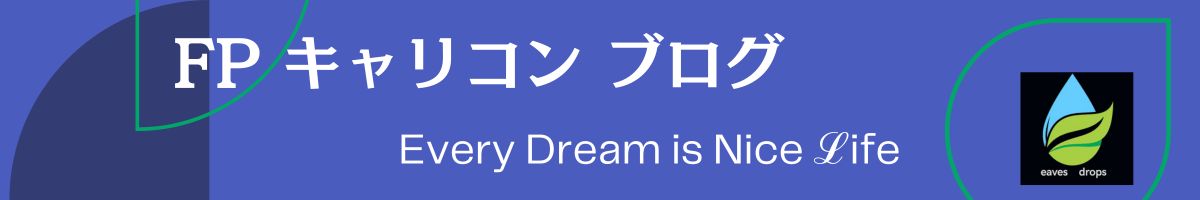


コメント