華やかな時代に隠された、もう一つの現実
「バブル景気」。煌びやかなディスコ、高騰する地価、誰もが浮かれていた時代――そんなイメージを抱いている若い世代もいるかもしれません。テレビや雑誌で語られるバブルは、まるで夢のような世界です。
しかし、もしあなたが地方で生まれ育ったなら、あるいは当時の地方の暮らしを少しでも知る機会があったなら、その印象は大きく異なるはずです。
メディアがこぞって伝えたバブルの恩恵は、残念ながら地方の隅々まで届いていたわけではありません。むしろ、都市部との格差をより鮮明にした側面すらあったのです。
今回は、バブル期における地方の、あまり語られない現実を紐解きながら、当時の暮らしが現代ほど安楽ではなかった事情を若い世代に伝えていきたいと思います。
高嶺の花だった「豊かな暮らし」
バブル期、確かに日本の経済は右肩上がりでした。しかし、その恩恵を実感できたのは、主に都市部、特に大企業の社員や不動産投資家など、一部の人々に限られていました。
地方の多くは、依然として第一次・第二次産業が中心であり、急激な景気変動の波に乗り切れていなかったのです。
想像してみてください。都市部では、海外ブランドのバッグや高級車が飛ぶように売れ、連日のように豪華なパーティーが開かれていたかもしれません。しかし、地方の商店街では、昔ながらの店主が細々と店を切り盛りし、人々は日々の生活に精一杯でした。高価な輸入品は、地方の平均的な収入からすれば、到底手の届かない「高嶺の花」だったのです。
今ほど安価ではなかった物価
現代の私たちは、ディスカウントショップや100円ショップに行けば様々なものが手に入り、ファストファッションで手軽に流行の服を楽しむことができます。しかし、バブル期はそうではありませんでした。大量生産・大量消費の仕組みは現在ほど確立しておらず、物価は今よりもずっと高く感じられました。
特に地方においては、物流コストなども加わり、都市部よりもさらに価格が高くなる傾向がありました。食料品、日用品、衣料品…生活に必要なものを揃えるだけでも、家計には大きな負担がかかっていたのです。安易な衝動買いなどできる余裕はなく、人々は物を大切に使い、質素な生活を送っていました。
限られた選択肢と情報
インターネットが普及していなかった当時、地方に住む人々が得られる情報や選択肢は限られていました。都市部で流行している商品やサービスの情報は、タイムラグが生じたり、そもそも地方には存在しなかったりすることも珍しくありませんでした。
例えば、最新の家電製品やファッションアイテムを手に入れるためには、わざわざ都市部まで足を運ぶ必要があったのです。情報もテレビや雑誌が中心であり、多様な価値観やライフスタイルに触れる機会は限られていました。現代のように、インターネットを通じて世界中の情報にアクセスし、比較検討しながら賢く消費するという行動は、一般的ではありませんでした。
変わらなかった人々の暮らし
バブル景気という言葉の華やかさとは裏腹に、地方の人々の生活は、劇的に変化したわけではありません。 朝から晩まで農作業に精を出す人々、地域の中小企業で地道に働く人々。彼らの日常は、派手な消費とは無縁の、地に足の着いたものでした。
もちろん、公共事業の増加などで一時的に潤った地域もあったかもしれませんが、それはバブルの恩恵というよりも、国の政策によるものが大きかったと言えるでしょう。そして、バブル崩壊後には、そうした一時的な恩恵も失われ、地方経済は再び厳しい状況に置かれることになったのです。
低賃金でも今の方が贅沢かもしれません
「今の若者は低賃金でかわいそうだ」という声を聞きます。確かに額面だけ見ればそうかもしれません。しかし、もしバブル期とほぼ同額の賃金で生活するとしたら、今の消費生活の方がずっと贅沢だと断言できます。
当時、今ほど安価な輸入品は少なく、外食やレジャーも高嶺の花でした。家電製品も高価で、一人一台スマホを持つなど考えられません。情報も限られ、選択肢は今よりずっと少なかったのです。
低賃金と言われながらも、私たちは多様な商品を手軽に購入でき、SNSで世界と繋がり、エンタメも豊富に享受できます。この利便性と選択肢の多さは、かつての高賃金時代には考えられなかった贅沢です。
大切なのは、額面の賃金だけでなく、その賃金で何が手に入るかという「購買力」です。そう考えると、私たちは意外と豊かな時代を生きているのかもしれません。
仕事においても劣悪な環境で耐え忍んだ時代
今では信じられないかもしれませんが、かつての会社では、理不尽な上下関係や劣悪な雇用条件が当たり前のように存在していました。上司のパワハラまがいの言動は日常茶飯事、サービス残業は「当たり前」、有給休暇など夢のまた夢。それでも皆、それを「当たり前」だと受け入れていたのです。
「嫌なら辞めればいい」? そんな言葉は通用しませんでした。転職は「我慢と努力が足りない落ちこぼれ」の烙印を押される行為。一度レールを外れれば、二度と這い上がれないという強烈なプレッシャーがありました。
当時の人は疑問を感じながらも声を上げることができませんでした。組織の論理が個人の尊厳を踏みにじり、未来への不安を抱えながら、ただひたすら耐え忍ぶ毎日。それは、今では考えられないほど息苦しい時代でした。
「当たり前」という名の呪縛に縛られ、個人の権利や幸福が置き去りにされていた時代だと言えます。
当時は「キャリア理論」なんて言葉、死語同然でした
今、「キャリア」という言葉は、就職活動や人事評価、個人の成長戦略など、ビジネスシーンで当たり前のように飛び交っています。キャリアパス、キャリアプラン、キャリアアップ…枚挙にいとまがありません。
しかし、あの劣悪な労働環境が「当たり前」だった時代、少なくとも私の周りでは、「キャリア理論」なんて言葉は、まるで遠い国の言葉、あるいは学者の書斎に眠る死語のような存在でした。
終身雇用が当たり前で、一度入った会社に骨を埋めるのが美徳とされていた時代です。個人の主体的なキャリア形成などという概念は、ほとんど存在しませんでした。会社が用意したレールに乗ることが、唯一の「正解」であり、そこから逸脱することは、異端者として扱われるリスクを伴いました。
転職という選択肢がネガティブに捉えられ、「我慢と努力が足りない」と断じられる風潮の中で、自分の「キャリア」を主体的に考え、行動することなど、想像すらできませんでした。目の前の仕事をこなすこと、会社の方針に従うこと、そして何よりも「辞めないこと」が最優先だったのです。
今、キャリア理論を学び、自身のキャリアを デザインしようと積極的に動く若い世代を見るにつけ、隔世の感があります。当時は、自分の将来を会社に委ねるのが当たり前。個人のWill(意志)やCan(能力)を осознавать(自覚)し、それを развитию(発展)させるという視点は、ほとんど皆無だったと言っても過言ではありません。
劣悪な環境に疑問を持ちながらも、キャリアという概念がないが故に、現状を打破する術を知らなかった私たち。それは、現代の働き方やキャリアに対する考え方とは、全く異なる世界だったのです。
若者たちへのメッセージ:表層的な情報に惑わされないで
若い世代の皆さんに伝えたいのは、メディアを通して語られる過去のイメージが、必ずしも全ての地域、全ての人々の現実を表しているわけではないということです。
バブル景気は、確かに一部の人々にとっては夢のような時代だったかもしれませんが、地方においては、日々の生活を守ることに精一杯だった多くの人々がいたことを忘れないでほしいのです。
現代の豊かな消費生活は、先人たちの努力や技術革新、そしてグローバルな経済システムの上に成り立っています。安価にものが手に入る今の時代は、決して当たり前ではありません。過去の地方の現実を知ることは、現代の豊かさの背景にある様々な要因を理解し、感謝するきっかけになるはずです。
そして、表層的な情報に惑わされず、多角的な視点から社会を見つめることの大切さを知ってほしいと願っています。華やかな物語の裏側には、語られない人々の暮らしや現実が必ず存在しているのですから。
にほんブログ村
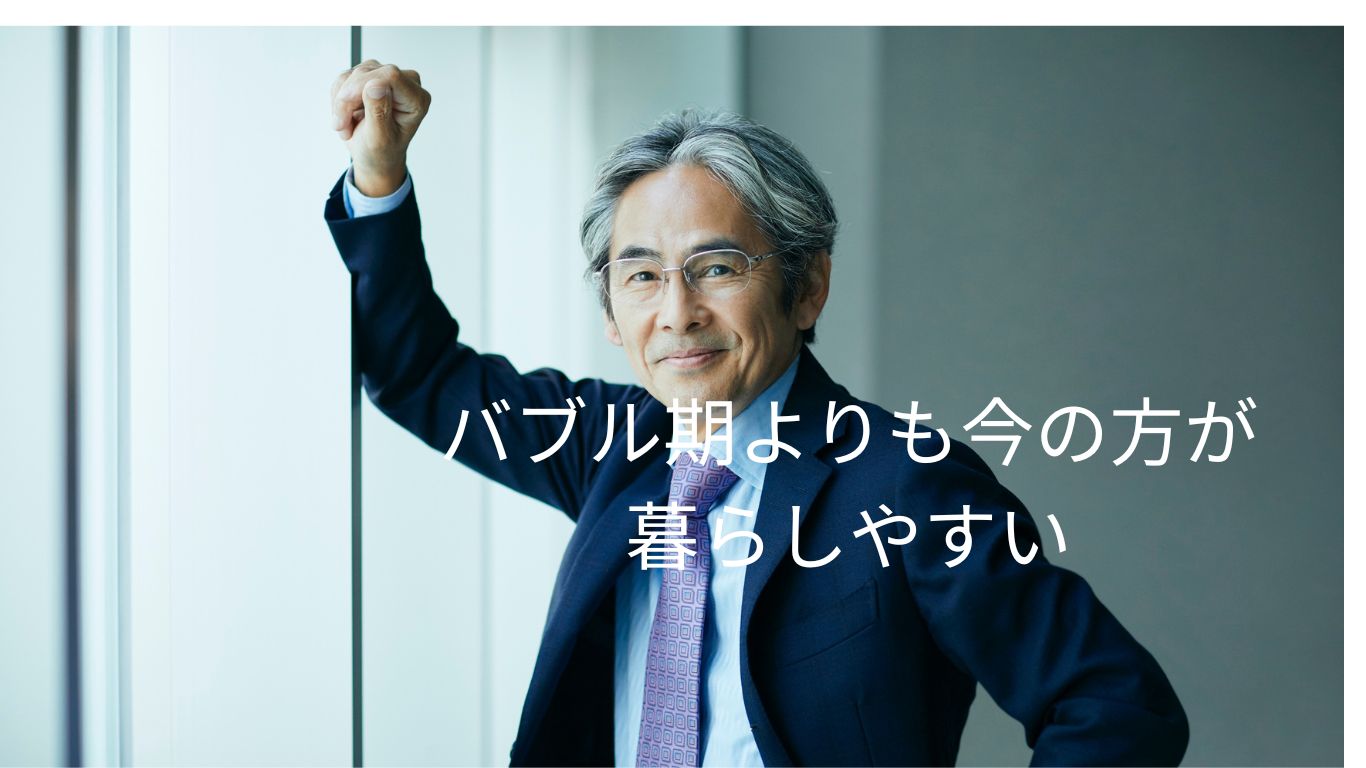
コメント