長年連れ添った夫婦が、いよいよ迎える年金生活。ゆっくりと二人の時間を楽しみたいけれど気になるのはお金のこと。特に、これまでの家計管理の方法を見直す必要性を感じている方は多いのではないでしょうか。
そこで提案したいのが、夫婦の年金額を「ほぼ完全に折半」するという、新しい家計のあり方です。これまで別々に管理してきた年金を、夫婦共通の財布に一旦集め、そこから二人の生活に必要な費用を出し合う。このシンプルな方法が、経済的な安心感だけでなく、夫婦の協力と尊重を育み、より円満なセカンドライフへと繋がるかもしれません。
今回は、この「年金折半家計」の具体的な方法と、食費やインフラ経費など、生活費の分担について、さらに現代的な視点を加えて考えていきましょう。
まずは「見える化」から!夫婦の年金額と主な支出を把握する
最初に、ご夫婦それぞれの年金収入額を正確に把握しましょう。年金定期便やねんきんネットなどを活用し、毎月受け取れる金額を確認します。
次に、現在の主な支出項目を洗い出します。
- 固定費: 住宅ローン(または家賃)、管理費、固定資産税、自動車関連費用(保険、税金、駐車場代)、生命保険料、通信費(スマホ、インターネット)、NHK受信料など
- 変動費: 食費、水道光熱費、医療費、日用品費、衣料費、趣味・娯楽費、交際費、交通費、お小遣いなど
これらの情報を整理することで、毎月の収入と支出のバランス、そしてどのくらいの金額を共通の財布に入れる必要があるのかが見えてきます。
「ほぼ完全に折半」の考え方と共通財布の作り方
「ほぼ完全に折半」とは、それぞれの年金収入から、必要最低限の個人のお小遣いを除いた金額を、夫婦共通の口座に預けるという考え方です。
例えば、夫の年金が月18万円、妻の年金が月10万円の場合、それぞれが月々2~3万円程度のお小遣いを確保し、残りの金額(夫:15万円、妻:7万円)を共通口座に入金します。
共通口座は、夫婦どちらかの名義でも、共有名義でも構いません。管理しやすい方法を選びましょう。
共通財布から支出する費目:食費、インフラ経費、住居費など
共通口座から主に支出する費目は、二人の生活に共通して必要なものとなります。
- 食費: 日々の食材購入費、調味料、米など
- インフラ経費: 水道光熱費(電気、ガス、水道)、通信費(固定電話、インターネット)
- 住居費: 住宅ローン返済または家賃、固定資産税、火災保険料、マンション管理費など
- 日用品費: 洗剤、トイレットペーパー、ティッシュペーパーなど
- 医療費: 夫婦共通で利用する医療費(個人の医療費は原則各自のお小遣いから)
- 趣味・娯楽費(共通のもの): 夫婦で楽しむ旅行費用、外食費用、映画鑑賞など
これらの費用を共通財布から支払うことで、どちらか一方に負担が偏ることを防ぎ、公平な家計運営が可能になります。
個人の支出と自由なお金:お小遣いの使い道
共通財布から支出しない費用、例えば個人の趣味に使うお金、衣料品、散髪代、個人的な交際費などは、それぞれが確保したお小遣いから支出します。
お小遣いの金額は、夫婦で話し合って無理のない範囲で決めましょう。大切なのは、お互いの自由になるお金を尊重し、干渉しすぎないことです。
予期せぬ支出への備え:共通の貯蓄も忘れずに
年金生活では、予期せぬ出費も起こりえます。病気や怪我による医療費、家電製品の故障による買い替え費用、家の修繕費用など、ある程度の金額が必要になることも考慮しておきましょう。
共通財布から毎月一定額を貯蓄に回すことで、いざという時に安心して対応できます。目標額を決めて、夫婦で協力して貯めていくことが大切です。
しかし、現在物価高進行中ですので貯蓄なんて難しいのが現実です。臨時出費が発生した場合退職金などがある場合はお互いに話し合って、その中から対処することも必要でしょう。
定期的な見直しと夫婦のコミュニケーション
年金生活に入ると、ライフスタイルや支出の状況も変化していきます。年に一度など、定期的に夫婦で家計を見直し、共通財布への入金額や支出項目、お小遣いの金額などを調整するようにしましょう。
何よりも大切なのは、お金のことについて夫婦でオープンに話し合い、お互いの意見や希望を尊重することです。共通の目標を持ち、協力して家計を運営していくことが、経済的な安定と夫婦円満の秘訣と言えるでしょう。
若い世代の共稼ぎ夫婦では当たり前!高齢者夫婦にもたらす新たなメリット
実はこの「年金折半家計」、若い世代の共稼ぎ夫婦の間では、すでに一般的な家計管理の方法となりつつあります。それぞれの収入をオープンにし、共通の目標に向かって協力し合うスタイルは、経済的な自立性を保ちながら、パートナーシップを深める上で理にかなっていると言えるでしょう。
そして、この考え方は、長年連れ添った高齢者夫婦にとっても、新たなメリットをもたらす可能性があります。
遠慮なく小遣いを使える関係へ
長年連れ添った夫婦であっても、お金のことはデリケートな話題になりがちです。どちらか一方が主に家計を担ってきた場合、「相手に負担をかけたくない」という遠慮から、本当に欲しいものを我慢したり、したいことを諦めてしまったりすることがあるかもしれません。
しかし、年金を折半し、共通の財布から生活費を出すことで、「自分のお金」という意識が薄れ、お互いに対してよりオープンに、そして遠慮なく小遣いを使えるようになるのではないでしょうか。「たまにはちょっと良いものを食べようか」「一緒に趣味の旅行に行こうか」といった提案も、気兼ねなくできるようになるかもしれません。
主婦の役割からの解放:新たな自由と可能性
特に、長年主婦として家計を支えてきた女性にとって、年金折半は大きな変化をもたらす可能性があります。これまでの「自分が家計を管理しなければ」というプレッシャーから解放され、より自由な時間を自分のために使えるようになるかもしれません。
限られた年金収入の中で、少しでも自分のやりたいこと(趣味、習い事、友人との交流など)を実現するために、お互いの自由になるお金を確保することは重要です。
干渉を減らし、シェアハウス的な夫婦生活のススメ
年金折半によって経済的な自立性が保たれると、お互いの個人的な領域への干渉も自然と減っていくかもしれません。共通の生活基盤は維持しつつも、それぞれの趣味や交友関係、時間の使い方に対して、より寛容になれるのではないでしょうか。
これは、まるで「シェアハウス」のような、程よい距離感を保った新しい夫婦の形とも言えるかもしれません。それぞれの個性を尊重し、干渉しすぎない関係性は、風通しの良い、居心地の良い空間を生み出し、結果的に夫婦円満の秘訣となる可能性を秘めています。
引き続き、基本的な考え方も大切に
もちろん、年金折半は万能ではありません。それぞれの収入額や価値観、ライフスタイルによって、最適な方法は異なります。記事の最初に述べたように、まずは夫婦でしっかりと話し合い、お互いが納得できる方法を見つけることが最も重要です。
しかし、固定観念にとらわれず、若い世代の新しい考え方も参考にしながら、これからの二人の生活をより豊かに、そして笑顔で満ち溢れたものにするために、年金折半という選択肢を検討してみてはいかがでしょうか。
新しい年金生活の門出に、ご夫婦での旅行はいかがでしょうか?
お薦めは、九州旅行です。
にほんブログ村
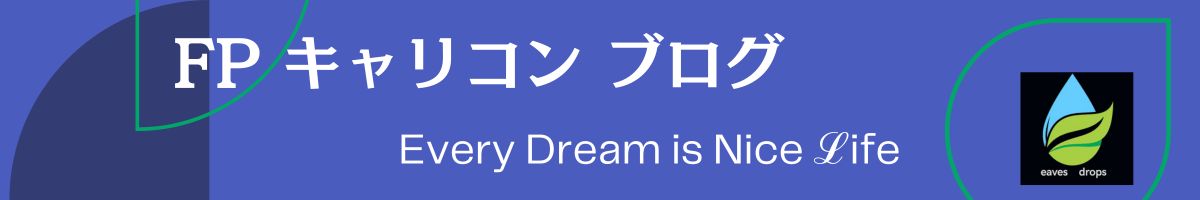

コメント