選挙が近づくと、各政党から聞こえてくる「賃上げをします」という力強い公約。物価高騰に苦しむ私たち国民にとっては、まさに希望の光のように聞こえるでしょう。しかし、この「賃上げ」という言葉の裏には、日本の経済を支える中小企業の厳しい現実と、政治の具体的な方策の欠如が横たわっています。そして、「若者が選挙に行かないから政治は変わらない」という声は、その本質を見誤っていると言わざるを得ません。
賃上げは「企業努力」の賜物、中小企業は綱渡り
大前提として、従業員の給与額を実際に決めて支払うのは企業です。政治家が「賃上げ」を公約しても、それはあくまで方向性を示すものであり、具体的な行動は各企業の経営判断に委ねられます。
政党が掲げる賃上げ策には、最低賃金の引き上げや、減税、社会保険料の軽減などで「手取りを増やす」政策が提唱されていますが、これらは間接的な支援に過ぎません。
特に、日本経済の屋台骨である中小企業は、この賃上げの波に大きな苦悩を抱えています。慢性的な人手不足に直面する中、人材を確保するためには、給与や福利厚生を充実させるしかありません。
しかし、これが直接的に人件費の高騰を招き、利益を圧迫。結果として、倒産に追い込まれる中小企業も少なくないのです。2014年上半期には、「求人難」や「人件費上昇」を理由とする倒産の半数が建設業であったように、特定の業界ではより顕著な問題となっています。
日本の民間企業の平均年収を見ると、中小企業(10~99人規模)では約336万円、中企業(100~999人規模)では約360万円と、大企業に比べて大きな差があります。
このような状況で、さらなる人件費高騰は、中小企業にとって死活問題となりかねません。政治の「賃上げ」公約は、具体的な企業支援策が伴わなければ、絵に描いた餅であり、むしろ中小企業を追い詰めるリスクすらあるのです。
公務員給与引き上げの波紋と地方の現実
では、公務員給与の引き上げは、民間企業にどの程度の波及効果をもたらすのでしょうか。国家公務員の賃金は、地方公務員だけでなく、公務員に準拠する約625.8万人の民間労働者にも直接影響を与えると指摘されています。これは日本の全労働者の1割以上を占める規模であり、その賃金動向は経済全体に影響力を持つとされます。
しかし、その波及効果は限定的であるという見方もあります。特に地方に目を向けると、公務員給与と民間企業の給与には大きな乖離が見られます。2023年度のデータでは、地方公務員の平均給与が月額約35.8万円(年収約430万円)であるのに対し、民間企業の平均給与は月額約26.2万円(年収約318万円)であり、その差は約116万円となっています。
地域や職種によっては「約200万円」もの差が生じることも十分にあり得る現実です 。公務員給与は人事院勧告に基づき、民間給与との均衡を図る「民間準拠」が原則ですが 、近年は「人材確保」の観点から若年層の初任給を大幅に引き上げるなど、戦略的な調整も行われています 。
この地方における公務員と民間企業の給与格差は、民間企業が賃上げに苦しむ中で、公務員だけが安定した高水準の給与を享受しているという不公平感を助長しかねません。
「若者が選挙に行かないから」は本末転倒
国会議員が賃上げを主張する背景には、物価高騰への対応や消費拡大による経済成長促進といった大義名分があります。しかし、その具体的な方策が欠けている現状は、国民の不信感を募らせるばかりです。
そして、この政治への不信感の根源を「若者が選挙に行かないから政治は変わらない」と、若者だけに責任を押し付ける声は、まさに本末転倒と言えるでしょう。
日本財団の18歳意識調査では、「政治はクリーンである」と答えた若者は1割程度に過ぎず、「国会議員は特権や優遇を多く受けている」と7割以上が感じています。OECDの調査でも、日本の政府への信頼度は加盟国中下位に位置しています。
このような状況は、中高年世代の長年にわたる政治への無関心や「誰かが何とかしてくれる」という他力本願的な姿勢、そして家庭教育や学校教育で「自分を大切にしたいなら周囲の人達のことも大切に考える」「政治について自分の事として考える」ということを若者に伝えられなかった責任も無関係ではありません。
実際、年代別の投票率を見ると、60歳代が71.38%であるのに対し、20歳代は35ポイント近く低いという大きな世代間ギャップが存在します。また、若者の政治への関心度が全体よりも低い傾向にあることや、家族と政治の話をする頻度が低いほど投票に行かない傾向があることも指摘されています。
家庭で政治や選挙について教えることの重要性は9割以上の親が認識しているものの、実際に教えているのは3割程度にとどまっているという調査結果もあります。
政治は国会議員や官僚が動かすものであり、国民一人ひとりが動かすものではないと考える若い世代の傾向は、過去の調査でも同様の水準でした。これは、政治への参加意識が低いだけでなく、政治が自分たちの手で変えられるという実感を持てない世代が長く続いてきたことを示唆しています。
国会議員が本当に賃上げを実現したいのであれば、単なるスローガンに終わらせず、中小企業が賃上げできるような経営環境の整備、例えば生産性向上のための投資支援、税制優遇、あるいは人手不足解消に向けた具体的な労働政策など、より実効性のある、地に足の着いた方策を提示し、実行していく責任があります。
そして、私たち国民一人ひとりが政治への関心を高め、主体的に関わる姿勢を持つことが、政治の透明性と責任を向上させ、若い世代が希望を持てる社会を築くための第一歩となるでしょう。
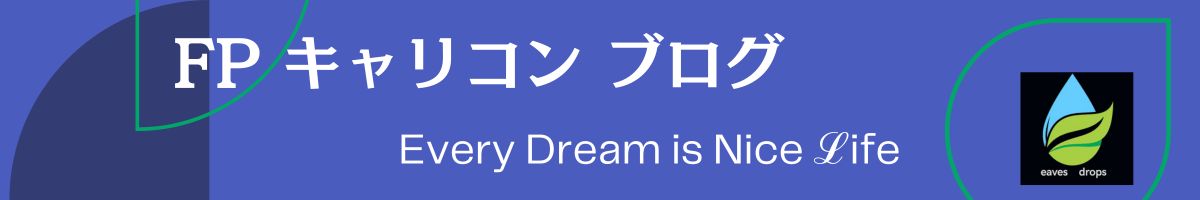
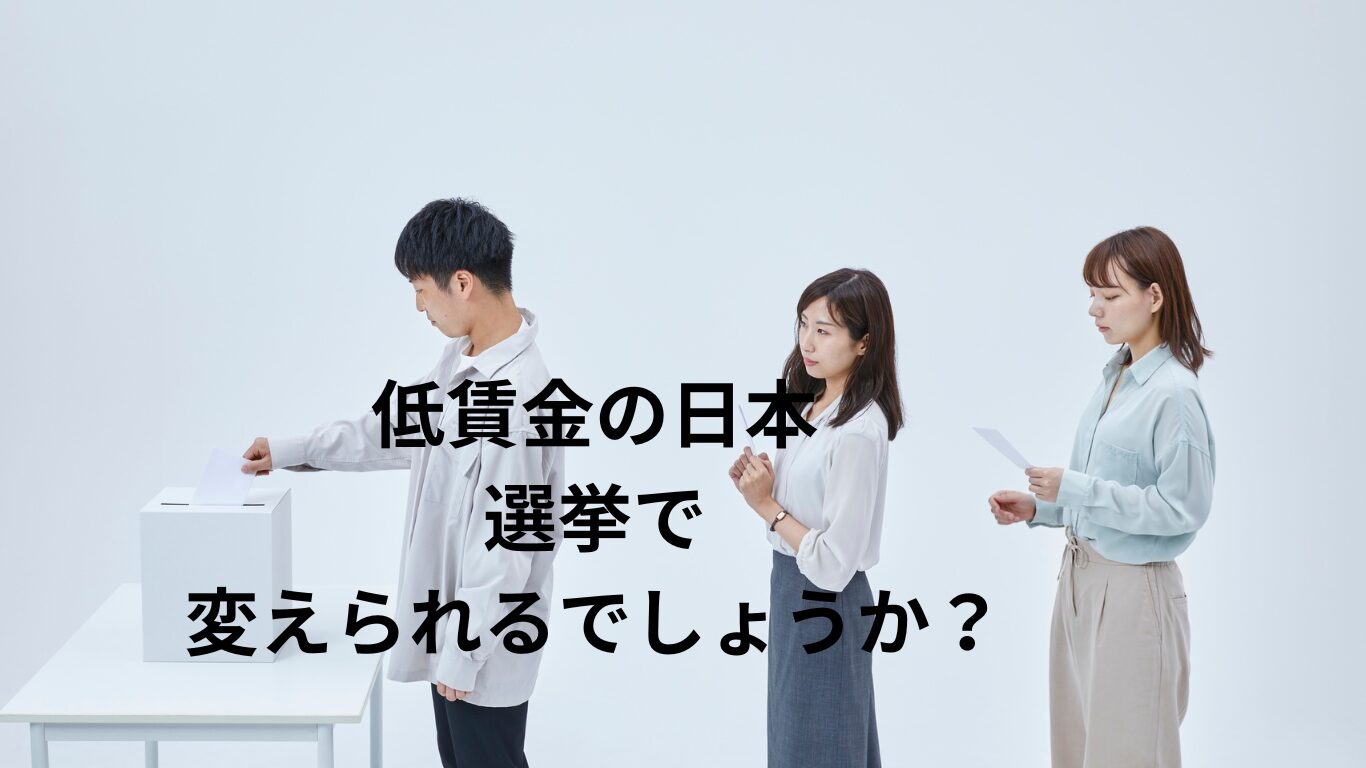
コメント