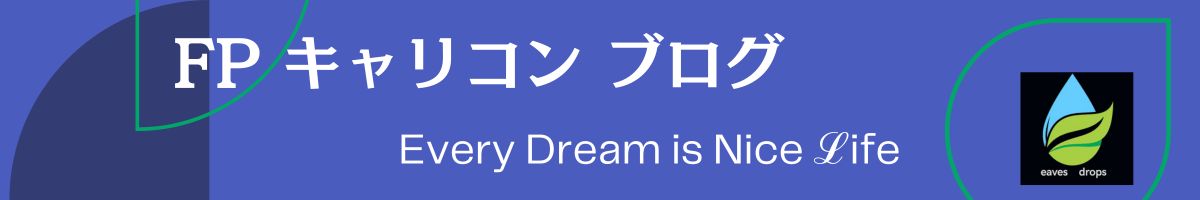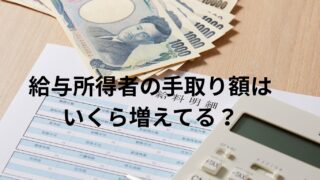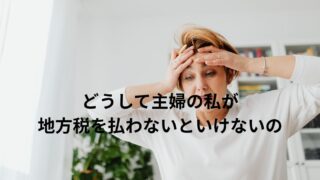 税金・年金
税金・年金 低所得の主婦にも地方税納税通知書が来たのは何故?
65歳の主婦の方から「夫の扶養に入っていて年金は年額90万円程度しかありません。住民税の納付書が来たのですがなぜですか」というご質問がありました。その理由は下記のとおりなのですが、介護保険も結構家計の負担になりますし、その上地方税まで支払わないといけません。生きづらい社会ですね。夫の扶養なのに住民税の納付書が来たのはなぜ?ご主人の扶養に入っていて、年金収入が年額90万円程度しかないのに住民税の納付書が届いたとのこと、驚かれたことと思います。結論から言うと、いくつかの理由が考えられますが、年金収入が90万円程度でも住民税が課税される可能性は十分にあります。住民税は、所得に対して課税される「所得割...