先日、ある農家さんと話す機会がありました。「スイカをサルに持っていかれた」とか「イノシシが害獣防止網の下の土を掘り起こしてお米を食べ、田んぼが荒らされた」など、なんとも気の毒な会話の中で、日本の主食であるお米の現状について、少しだけ真実を知りました。
価格上昇が農家さんの収入に結びつかない現実
最近、「お米の価格を上げて、生産者の収益アップを図り、農業の衰退に歯止めをかける」という話を聞くことがあります。消費者としては、日本の農業を守るために必要なことだと受け止めがちです。
しかし、農家さんの話を聞くと、この些細な価格上昇が生産者の懐にほとんど届いていない現実が見えてきます。
その農家さんがJA(農業協同組合)に出荷しているお米の買取価格は、5キログラムあたり約1,300円だそうです。しかも、これはこの地域で最もおいしいとされる一等米のコシヒカリです。この価格でも「少しは上がってきた」とのこと。
一方、私たちがスーパーなどで購入する際、同じお米は3,800円以上で売られています。もちろん、精米代や運送費、人件費、そして小売店の利益など、さまざまな経費が上乗せされるのは当然です。しかし、それにしても買取価格の3倍近くにもなる価格差は、正直信じられない思いでした。
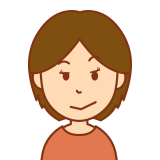
一等米とはいっても一袋内に70%以上の一等米が入っていれば「一等米」として販売できるそうです。つまり一等米以外のお米も混入しているということです。ただ個人経営の良心的なお米屋さんでは含有量の100%が一等米だそうです。少し値が張るようですが。
農家さんがお米を売る価格は、JAなどの買取価格によって決まります。最終的に私たちの食卓に届くまでの価格は、途中の流通段階で大きく膨らむのです。
この仕組みでは、どれだけ消費者が高いお金を払っても、生産者の収入にはほとんど影響がありません。これでは、高齢化が進み、後継者不足に悩む日本の農業を守ることは難しいでしょう。
日本の安全でおいしいお米は、誰が食べるのか?
この現状を踏まえると、これから日本の食がどうなっていくのか、懸念を抱かずにはいられません。
政府は、日本の高品質な農産物を海外に輸出する政策を推進しています。国内消費量分が十分賄えていればこれ自体は素晴らしいことです。しかし、裏を返せば、高価で安全、そしておいしい日本のコメは、これからますます海外で消費されるようになる可能性があります。
そして、その代わりに、私たちは海外から輸入される安価なお米を食べるようになるかもしれません。安全性が不透明であったり、味の劣るお米が主流になるのではないか、という懸念は拭えません。
今の日本の農家さんが丹精込めて作ったおいしいお米が、いつまで私たちの食卓に並び続けるのか。それは、決して当たり前のことではないのです。
私たちには見えない農家さんの苦労
お米を栽培する苦労は、並大抵のものではありません。
- 気候変動: 記録的な酷暑や水不足、突然の水害など、天候に左右されるリスクが年々高まっています。
- 病害虫・害獣: 獣害対策や病害虫の駆除は、農家さんの大きな負担となっています。
- 重労働とコスト: 高齢化による体力的な限界、そして高騰する農機具や燃料のコストも、経営を圧迫しています。
お米の価格が上がったとはいえ、これら見えない苦労を考えると、決して十分な対価とは言えないでしょう。
まとめ
私たちは今、当たり前のように日本のおいしいお米を食べることができていますが、その裏には農家さんの絶え間ない努力と、不安定な農業経営という現実があります。
この先、私たちが当たり前のように日本の一等米を食べる時代が終わるかもしれません。
だからこそ、私たちはスーパーに並んでいるお米が、どれほどの苦労を経て私たちの元に届いたのかを想像し、感謝の気持ちを持って大切にいただくべきではないでしょうか。そして、日本の農業を守るために、自分たちに何ができるのかを、一人ひとりが考える必要があるでしょう。
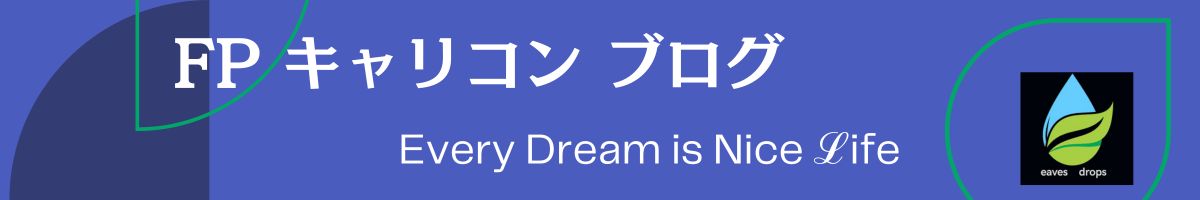


![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3fcc1fd7.ba6d96b3.3fcc1fd8.c461efd9/?me_id=1366602&item_id=10000450&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ff173860-hodatsushimizu%2Fcabinet%2Fyui2025%2F38601136_skua.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント