定年退職後も、長年の経験や知識を活かして社会と繋がり続けたいと考える方は少なくありません。しかし、再就職にあたっては、社会保険や税金といった現役時代とは異なる制度を理解し、賢く対応することが重要です。
定年退職者が再就職する際に、社会保険料、税金を節約するための働き方について、具体的な収入額と税額の例を挙げながら5分で読めるように解説します。
社会保険料を節約する働き方
定年退職後の社会保険は、働き方によって加入する制度や保険料が大きく変わります。賢く働くことで、社会保険料の負担を抑えることが可能です。
(1) 短時間労働(パート・アルバイト)で働く
節約のポイント:
- 労働時間と収入を調整する: 以下の条件を満たす場合、原則として会社の社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する義務はありません。
- 1週間の所定労働時間が20時間未満
- 月額賃金が8.8万円未満(令和6年10月以降は変更の可能性あり)
- 国民健康保険・国民年金に加入する: 会社の社会保険に加入しない場合は、国民健康保険と国民年金に自身で加入することになります。国民年金保険料は一律ですが、国民健康保険料は所得や自治体によって異なります。
収入と保険料の例:
- ケース1: 週15時間、月額7万円のパートで働く場合
- 会社の社会保険には加入せず、国民健康保険と国民年金に加入。
- 国民年金保険料:月額約1万6千円(令和6年度)
- 国民健康保険料:前年の所得に応じて変動(年間数万円~数十万円程度)
- 社会保険料の合計(概算):年間20万円~数十万円程度
- ケース2: 週30時間、月額15万円のパートで働く場合
- 原則として会社の社会保険に加入。
- 社会保険料(健康保険・厚生年金):月額2万円~3万円程度(収入や年齢によって変動)
- 社会保険料の合計(概算):年間24万円~36万円程度
このように、労働時間と収入を調整することで、会社の社会保険への加入を回避し、国民健康保険・国民年金に加入することで社会保険料の負担を抑えることが可能です。
国民健康保険料は前年の所得によって大きく変動するため、注意が必要です。
(2) 個人事業主・業務委託として働く
節約のポイント:
- 雇用保険の適用外: 個人事業主や業務委託契約の場合、雇用保険の適用はありません。
- 社会保険は原則として国民健康保険・国民年金: 一定の条件を満たさない限り、会社の社会保険に加入することはできません。
収入と保険料の例:
- ケース3: 年間の事業所得が200万円の個人事業主の場合
- 国民健康保険料:所得や自治体によって変動(下記の国民健康保険料の算定についてをご覧ください)
- 国民年金保険料:月額約1万6千円(令和6年度)
個人事業主や業務委託は、働く時間や場所を自由に決めやすい反面、収入が不安定になる可能性や、社会保険を全て自分で負担する必要がある点に注意が必要です。
国民健康保険料の金額の算定について
今年度の国民健康保険料の金額は、以下の要素に基づいて決定されます。これらの要素は各自治体によって細部が異なる場合があります。
人口24万人の地方自治体の一例です。令和7年度の料率で保険料の算定例は次のとおりです。
医療分保険料所得割額:(前年の所得金額 – 43万円)× 8.8%(年額)
均等割額:1人につき 25,000円(年額)
平等割額:1世帯につき 21,900円(年額)
上限額:66万円
後期高齢者支援金分保険料
所得割額:(前年の所得金額 – 43万円)× 2.7%(年額)
均等割額:1人につき 8,800円(年額)
平等割額:1世帯につき 5,800円(年額)
上限額:17万円
介護分保険料(40歳から64歳までの加入者のみ)
所得割額:(前年の所得金額 – 43万円)× 2.8%(年額)
均等割額:1人につき 8,100円(年額)
平等割額:1世帯につき 7,100円(年額)
上限額:26万円
あなたの保険料を概算する場合に必要な情報
ご自身の今年度の国民健康保険料を概算するためには、以下の情報が必要です。
- 前年の所得金額: 令和6年1月1日から令和6年12月31日までの総所得金額などから基礎控除(通常は43万円)を引いた額。源泉徴収票や確定申告書などで確認できます。
- 世帯の国民健康保険加入者数: あなたを含め、同じ国民健康保険に加入する人数。
- 世帯の状況: 平等割がある場合、世帯に一律で課税されます。
- 年齢: 40歳から64歳の方は、介護保険料が加算されます。
- お住まいの市区町村の国民健康保険料率: 上記の所得割率、均等割額、平等割額は自治体によって異なります。
保険料の軽減制度
所得が低い世帯に対して、国民健康保険料の均等割額や平等割額が軽減される制度があります。軽減割合は世帯の所得や加入者数などによって異なり、7割、5割、2割軽減などがあります。
税金を節約する働き方
定年退職後の税金は、現役時代とは異なる控除制度などを活用することで、負担を軽減できる場合があります。
(1) 公的年金と再就職収入のバランスを考える
節約のポイント:
- 公的年金等の収入額と再就職収入額を調整する: 所得税や住民税は、年間の所得に応じて課税されます。公的年金等の収入と再就職による収入の合計額を考慮し、税負担が過度にならないように収入を調整することが有効です。
- 年金収入にかかる税金: 公的年金収入には、所得税と住民税がかかります。ただし、公的年金等控除という所得控除があり、年金収入額に応じて控除額が変動します。
収入と税金の例:
- ケース4: 年間の公的年金収入が200万円、再就職による給与収入が100万円の場合(65歳未満)
- 公的年金等控除額:70万円
- 給与所得控除額:55万円
- 所得金額:(200万円 – 70万円) + (100万円 – 55万円) = 175万円
- 所得控除額(基礎控除、社会保険料控除などは考慮せず):48万円(基礎控除)
- 課税所得金額:175万円 – 48万円 = 127万円
- 所得税額(概算):約6万円
- 住民税額(概算):約12.7万円
- 所得税・住民税の合計(概算):約18.7万円
- ケース5: 年間の公的年金収入が200万円、再就職による給与収入が50万円の場合(65歳未満)
- 所得金額:(200万円 – 70万円) + (50万円 – 55万円) = 125万円(給与所得は5万円で計算)
- 所得控除額(基礎控除、社会保険料控除などは考慮せず):48万円
- 課税所得金額:125万円 – 48万円 = 77万円
- 所得税額(概算):約3.8万円
- 住民税額(概算):約7.7万円
- 所得税・住民税の合計(概算):約11.5万円
再就職による収入を抑えることで、所得金額が減り、結果的に所得税と住民税の負担を軽減できることがわかります。
(2) 各種所得控除を最大限に活用する
節約のポイント:
- 生命保険料控除、医療費控除、扶養控除など: これらの所得控除は、所得金額から差し引かれるため、課税所得金額を減らし、所得税と住民税を節約する効果があります。再就職後も、これらの控除を忘れずに申告しましょう。
- 配偶者控除・配偶者特別控除: 配偶者の所得金額に応じて、これらの控除を受けることができます。再就職後の働き方によっては、配偶者の所得金額が変動する可能性があるため、確認が必要です。
(3) iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)の活用
節約のポイント:
- 掛金が全額所得控除: iDeCoに拠出した掛金は、全額所得控除の対象となります。これにより、所得税と住民税を節税することができます。
- 運用益が非課税: iDeCoで運用した利益には、通常かかる所得税がかかりません。
- 受取時にも税制優遇: iDeCoの給付金を一時金として受け取る場合や、年金として受け取る場合にも、税制上の優遇措置があります。
再就職後もiDeCoへの加入資格がある場合は、積極的に活用することで、将来の資産形成と税金節約を両立できます。
⇒ こちらの記事もご参考に「地方移住後の節約対策 まずは節税から始めよう」
まとめ:賢い働き方で、ゆとりあるセカンドライフを
定年退職後の再就職は、社会との繋がりを保ち、経済的な安定を得るための有効な手段です。しかし、社会保険や税金の仕組みを理解し、ご自身のライフスタイルや収入に合わせて賢く働くことで、手取り額を増やし、よりゆとりのあるセカンドライフを送ることが可能になります。
今回のブログ記事が、定年退職後の働き方を検討する上で、少しでもお役に立てれば幸いです。ご自身の状況に合わせて、最適な働き方を見つけてください。
(注)
- 上記の社会保険料や税額はあくまで概算であり、個々の収入や控除額、自治体によって異なります。
- 税制や社会保険制度は改正される可能性がありますので、最新の情報を必ずご確認ください。
にほんブログ村
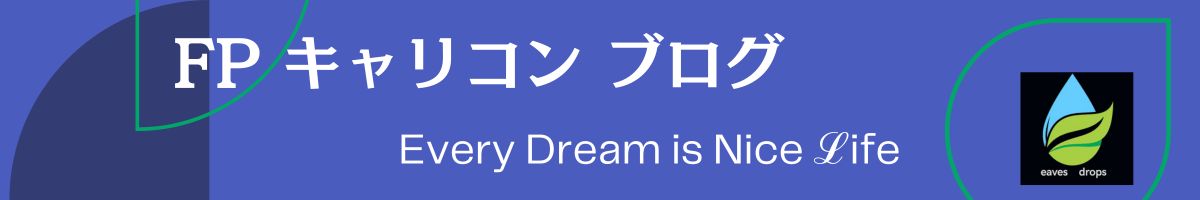
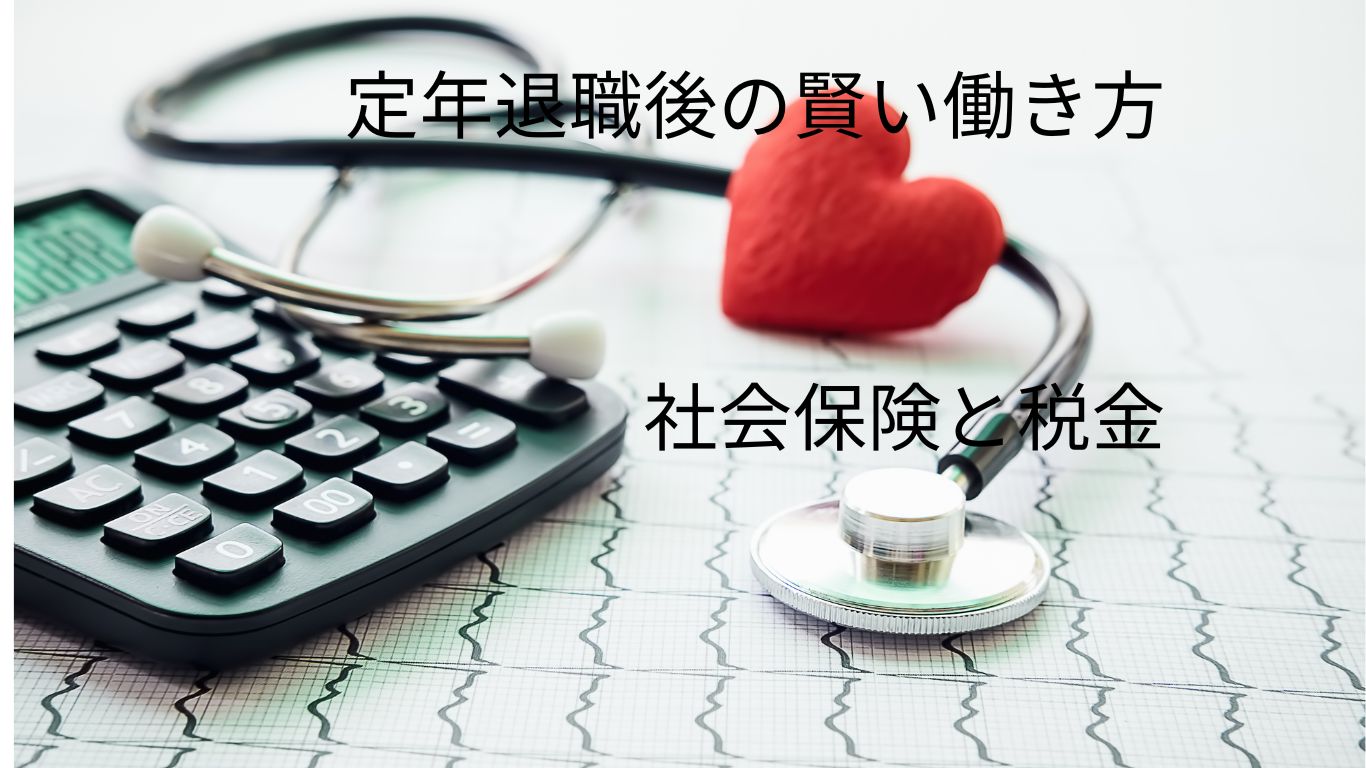
コメント