こんにちは!今回は、ニュースなどで耳にする「特別会計」について、その「闇」と呼ばれる実態をわかりやすく解説します。
特別会計とは何か?「闇」と呼ばれる理由
日本の国の会計は大きく「一般会計」と「特別会計」に分かれています。「一般会計」は、税金などから集めたお金を、教育や防衛、社会保障など、国全体の基本的な活動に使うための財布です。私たちが普段「国の予算」として耳にするのは、ほとんどがこの一般会計のことです。
一方、「特別会計」は、特定の事業を行うために、特定の収入を充てることを目的として設置される会計です。例えば、年金や労災保険、高速道路の整備など、国が手がける特定の事業のための専用の財布だと思ってください。
では、なぜこれが「闇」と呼ばれるのでしょうか?
その理由は、特別会計の仕組みが非常に複雑で不透明だからです。
- 💰巨大な規模と複雑な仕組み:特別会計の予算規模は一般会計を大きく上回ることが多く、その総額は国の予算全体の3分の2にもなると言われています。しかし、そのお金がどのように使われているのか、一般の国民にはほとんど見えません。さらに、会計の種類が50以上もあり、それぞれが異なるルールで運営されているため、全体像を把握するのが非常に困難です。
- 🔄非効率な資金の流れ:特別会計の中には、無駄な資金の積み立てや、本来の目的とは異なる使われ方をしているケースがあると指摘されています。また、会計間で資金のやり取りが行われることがあり、その流れがブラックボックス化しているため、無駄遣いや不正の温床になりやすいのです。
- 🕵️♀️チェック機能の不備:特別会計の多くは、国会での審議が一般会計ほど厳格に行われません。そのため、国民の目が届きにくく、政府による自由な裁量が働きやすくなっています。
これらの理由から、特別会計は「見えない巨額の財源」として「闇」と呼ばれているのです。
「闇」を解明し、政府に挑んだ人々
この特別会計の不透明な実態にいち早くメスを入れ、国民にその存在を訴え続けた人物がいます。それが、元参議院議員でタレントとしても活躍していた大橋巨泉氏です。
巨泉氏は、政界引退後もブログなどで精力的に特別会計の問題を追及しました。彼は、国民の血税がどのように使われているのか、なぜこれほど不透明な仕組みになっているのか、その構造的な問題点をわかりやすい言葉で解説し、多くの人々に特別会計の存在を知らせました。
そして、この問題に政党として本格的に取り組んだのが、日本維新の会(当時はおおさか維新の会)です。
特に、国会議員となった松井一郎氏や馬場伸幸氏らが中心となり、特別会計の廃止や統合、国会での透明性の向上を強く主張しました。彼らは、国の予算の無駄を徹底的に洗い出す「身を切る改革」の一環として、特別会計を重要な改革対象と位置づけ、具体的な法案の提案や国会質疑を通じて、政府にその解明を迫ったのです。
また、もう一人、この「闇」に果敢に挑んだ人物がいます。それが、衆議院議員の石井紘基氏です。彼は、政治家になる前から膨大な資料を読み解き、国の裏側で行われている不正や利権の構造を徹底的に調査していました。
石井氏は、特別会計や特殊法人を「第二の予算」と呼び、その不透明な資金の流れを鋭く追及しました。彼は、「財政再建の鍵は特別会計にある」と訴え、国会で何度もこの問題を指摘しました。しかし、2002年、自宅前で右翼団体構成員に刺殺されるという衝撃的な事件によって、その活動は絶たれてしまいます。
石井氏を刺殺したのは右翼団体の男で、裁判では個人的な恨み(根拠のない金銭トラブル)が動機とされました。しかし、石井氏が命を落とす直前まで特別会計に関する資料をまとめていたことや、自宅に侵入した形跡があったことなどから、事件の背景には特別会計の利権が絡んでいるのではないかという憶測が生まれました。
それ以後しばらくの間「闇」の追及をする議員はいなくなったといわれています。怖い話ですね。
しかし、最近では増税や消費税の問題が取り上げられると特別会計の不透明さについても、個人や政党が解明と追及をしていますので、ようやく国民の間でもこの問題への関心が高まり始めました。
「特別会計の闇」について言及している政党
参政党
参政党は、特別会計を「国民の目を欺く『特別会計の闇』」として捉え、その問題を厳しく追及しています。彼らの主張は、特別会計が、本来国民の福祉のために使われるべき資金であるにもかかわらず、各省庁の官僚の天下り先を確保するための「特殊法人の投資事業」に使われている側面がある、というものです。
このような主張は、特別会計が官僚主導で運用され、利権の温床となっているという批判と一致しており、国民負担を減らすためにも、この問題の是正が必要だと訴えています。
れいわ新選組
れいわ新選組も、特別会計の問題を認識し、国の財政に関する政府の「ウソ」を否定する立場をとっています。
彼らは「国の借金は国民が返さなければいけない」「税金だけが財源である」といった政府の宣伝を「ウソ」だとしており、その背景には、富裕層を優遇する税制や、国民から搾り取った税金が不透明な形で使われている特別会計の問題がある、と示唆しています。
彼らの政策は、消費税の廃止や富裕層への課税強化を軸としていますが、これらの政策と合わせて、特別会計の問題にも言及することで、国の財政全体における不透明な部分を是正し、国民のための財政政策を実現しようとしています。
立憲民主党
立憲民主党は、特別会計の改革を重要な政策課題の一つとして位置づけています。
- 「埋蔵金」の発掘と活用: 特に、**外国為替資金特別会計(外為特会)**の剰余金や積立金に着目し、これを一般会計に繰り入れて国民の負担軽減や社会保障の財源に充てるべきだと主張しています。
- 財政の透明性向上: 特別会計の財務状況や運用実態を徹底的に見直し、国会への報告を義務付けることで、透明性の確保を目指しています。
- 無駄な予算の見直し: 肥大化した政府基金や官民ファンド、特別会計をスリム化し、歳出削減に取り組む姿勢を示しています。
日本維新の会
日本維新の会も、行政改革の一環として特別会計の見直しを強く訴えています。
- 「身を切る改革」: 議員報酬のカットや議員定数削減といった「身を切る改革」と並行して、特別会計の剰余金等を活用し、復興増税や国民への負担増を避けることを主張しています。
- 会計制度の抜本的見直し: 「財政の見える化」のため、国の財政状況を分かりにくくしている特別会計について、抜本的な見直しと整理を行うことを公約に掲げています。具体的には、公会計制度に民間企業で用いられる発生主義会計と複式簿記を導入することで、資産・負債を明確にし、財政の透明性を高めることを目指しています。
- 官民ファンド・基金等の整理: 官民ファンドや政府関係法人の民営化を進めることで、特別会計の硬直した予算配分を見直し、財政の健全化を図るとしています。
特別会計と一般会計、予算規模の比較
日本の国家予算は、一般的な経費を扱う一般会計と、特定の事業に使われる特別会計に分かれます。
- 一般会計:およそ115兆円(令和7年度当初予算案)
- 特別会計(歳出総額):およそ492兆円(令和7年度当初予算案)
この数字を比較すると、特別会計の予算規模(歳出総額)は、一般会計の約4.3倍となり、「5倍」という表現は実態に近いと言えます。
特別会計の歳出総額が一般会計よりはるかに大きいのは、**会計間の資金のやりとり(重複)**があるためです。
例えば、一般会計から特別会計へ資金を繰り入れたり、特別会計同士で資金をやり取りしたりするケースが多数あります。この重複分を差し引いた数字を「歳出純計」といい、これが国の財政全体をより正確に表すと言われています。
この重複分を除いた特別会計の予算額(歳出純計)は、およそ204兆円となり、単純な比較では約1.8倍となります。
したがって、「5倍」という数字は、会計上の総額を比較した場合は正しいですが、国の財政規模全体を把握する上では、重複を考慮した「歳出純計」の数字で見るのがより適切です。
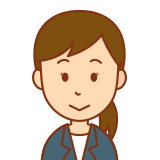
「特別会計同士で資金をやり取りしたりするケース」ってなんだか怪しいそうだけど
収支決算報告書はちゃんと作成れているのかな~
何に使われたじゃなくて、そのお金の流れを私たちは知りたいんですけど。
特別会計の収支決算報告は、法律に基づいて100%実施されていますということになっています。
日本の特別会計は、一般会計と同様に、法律(「特別会計に関する法律」など)によって厳格に管理されており、決算報告の義務が明確に定められています。
決算報告の流れ
- 所管大臣による作成: 各特別会計を所管する大臣は、毎年度、歳入歳出決算を作成し、財務大臣に送付することが義務付けられています。
- 内閣による提出: 財務大臣は、これらの決算をまとめて内閣に提出します。
- 会計検査院の検査: 決算は、内閣から会計検査院に送られ、その適法性や効率性、妥当性について厳格な検査を受けます。
- 国会への提出: 会計検査院による検査を経た上で、決算は国会に提出され、最終的な承認を得ます。
「不透明さ」の所以
決算報告自体は法律通りに行われていますが、それでも「特別会計の闇」と言われるのは、その運用の実態や資金の使途が国民には分かりにくいという点にあります。
- 複雑な会計構造: 特別会計は一般会計や他の特別会計との間で複雑な資金のやりとりを行うことがあり、全体像の把握が困難です。
- 不必要な剰余金や積立金: 法律上は問題なくとも、事業目的を終えた後も多額の資金が積み立てられたままになっていることがあり、その必要性が疑問視されています。
これらの問題点は、会計検査院の報告書などによってたびたび指摘されており、その指摘を受けて特別会計の統廃合や剰余金の一般会計への繰り入れが進められてきました。つまり、報告が行われているからこそ、不透明な部分が明らかになり、改革の必要性が議論されているのです。
消費税は一般会計予算に入っています
消費税は、所得税や法人税と並び、国の主要な税収の一つとして、一般会計の歳入の大部分を占めています。消費税収は、社会保障費、教育、公共事業、防衛費など、国の基本的な活動に必要な経費の財源として幅広く使われています。
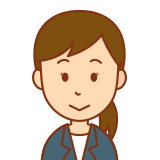
消費税って社会保障費のために使うって聞いたけど、一般会計なので何にでもいいことになっているの。
消費税が導入された当初は、その税収を福祉目的だけに使うという議論もありましたが、現在は一般会計の歳入として一括管理され、使途は特定されていません。
消費税は一般会計の歳入として扱われるため、特定の目的(例:社会保障)のみに使うと法律で定められてはいません。これが「使途が特定されていない」ということです。
税金の使途と「ひも付き」
税金には、使途が法律で定められている特定財源と、使途が定められていない一般財源があります。
- 特定財源: 目的税とも呼ばれ、集めた税金が特定の事業に充てられることが法律で決まっています。例えば、入湯税は環境衛生や観光振興に使われます。
- 一般財源: 消費税や所得税のように、特定の使途が定められておらず、社会保障、教育、公共事業、防衛など、国の様々な経費に広く使われます。
消費税と社会保障の関係
消費税は「社会保障の安定財源」として位置づけられていますが、これは法律で消費税収のすべてを社会保障だけに使うと定められているわけではありません。政府の予算編成の際に、税収全体の中で社会保障費を優先的に賄うという考え方で使われています。
つまり、消費税収が社会保障費の「ひも付き」になっているわけではなく、一般会計の歳入として他の税収と合算され、様々な政策のために使われているのが現状です。
消費税は「社会保障の安定財源」とされていますが、これはあくまで予算編成上の考え方です。具体的には、消費税収が増えた分、社会保障費に優先的に配分するというものです。
しかし、これは法律で消費税収の全額を社会保障に使うと定められているわけではありません。そのため、消費税収が社会保障以外の目的にも使われることは起こりえます。
法人税を減額した分、消費税を上げていますが、その理由は
法人税を減税し、消費税を増税する理由は、主に経済の活性化と安定した社会保障財源の確保という2つの目的を同時に達成しようとするためです。
1. 企業の国際競争力強化と経済活性化
法人税は、企業の利益に対してかかる税金です。これを引き下げることで、企業は手元に残る資金を増やし、それを設備投資、研究開発、賃上げなどに回すことが期待されます。これにより、企業の競争力が高まり、経済全体の成長に繋がると考えられています。
2. 社会保障の安定財源確保
消費税は、すべての世代が広く負担する税金であり、景気の変動に左右されにくい安定した税収源です。急速に進む少子高齢化によって社会保障費(年金、医療、介護など)が増え続ける中、その財源を確保するために消費税が適しているとされています。
この考え方は、「社会保障の安定財源化」と呼ばれています。政府は、消費税増税分を全額社会保障に充てることで、将来世代に負担を先送りせず、持続可能な社会保障制度を築くことを目指しています。
法人税減税と消費税増税は、一見すると矛盾しているように見えますが、両者はそれぞれの目的を達成するためのセットとして進められてきました。
- 法人税減税:企業活動を活発化させ、経済全体のパイを大きくする
- 消費税増税:増大する社会保障費を安定的に賄う
この政策は、国民の間で賛否両論があります。法人税減税は、大企業を優遇しているという批判や、実際に賃上げや投資に繋がっていないという指摘もあります。一方で、消費税増税は低所得者ほど負担が重くなるため、税の公平性の観点から問題視する声があります。
自民党は経済界と緊密な関係を築き、企業活動を後押しする政策を多く打ち出しました。その結果として、法人税の減税や補助金といった「法人優遇」と見なされる政策が推進されました。それはあくまで経済成長という目的を達成するための手段ですが、残念ながら多くの国民の貧困化という最悪の「歪み」を生じることになりました。
私たちはどうすればよいのか?
では、この巨大な「闇」を前に、私たち国民はどうすれば良いのでしょうか?
大切なのは、決して他人事だと思わないことです。特別会計に使われているお金は、私たち一人ひとりが納めた税金や保険料です。私たちが無関心でいると、そのお金がどのように使われているのか、誰もチェックできなくなってしまいます。
私たちができることは、以下の3つです。
- 🤔関心を持つこと:まず、特別会計という存在を知り、「なぜこんなに複雑でわかりにくいのか」という疑問を持つことが第一歩です。ニュースや政治家の発言に注意を払い、国の財政に関心を持つようにしましょう。
- 🗳️声を上げること:政治家や政党に、特別会計の透明化や改革を求める声を届けましょう。選挙の際には、この問題に真剣に取り組んでいる候補者や政党を支持することも重要です。
- 🤝監視すること:国会での予算審議や決算報告をチェックし、政府が特別会計をどのように運営しているか監視する目を持ちましょう。
特別会計の問題は、私たちの未来の財政に直結する大きな問題です。この「闇」を解き明かし、より透明で公正な財政運営を実現するためには、私たち国民一人ひとりの関心と行動が不可欠です。
今こそ、国の財政に目を向け、私たちの未来を守るための第一歩を踏み出しましょう!
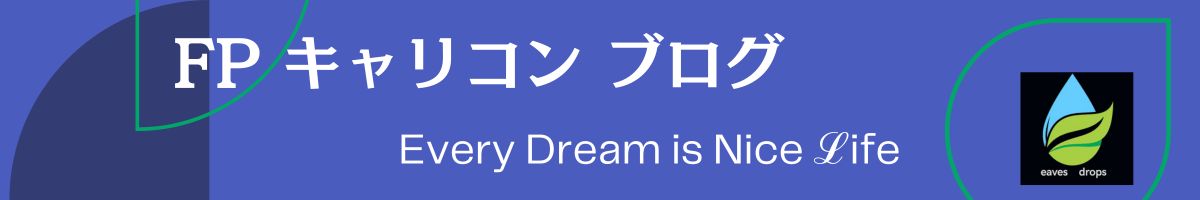
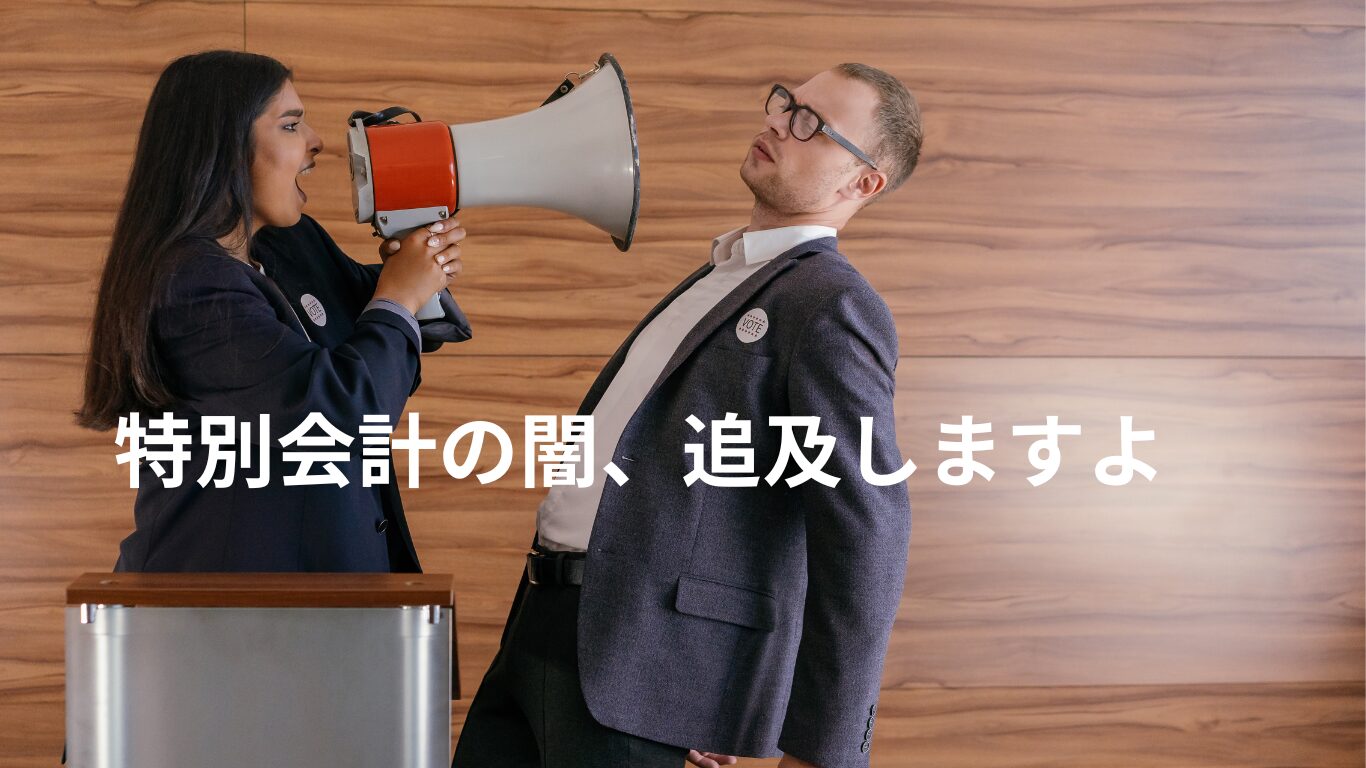
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4107e54d.ef851347.4107e54e.400bc2e0/?me_id=1251035&item_id=26730880&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhmvjapan%2Fcabinet%2Fa51%2F96000%2F15195001.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)


コメント